1
ここ四、五日続いた吹雪はようやく止んだが、海はまだ荒れていた。マフラーで頬かぶりはしていても、左の頬がひどく痛い。津軽海峡の風が、うなりをたててそちらから吹きつけるのだ。
さえぎるものは何一つない。ところどころに人家は点在しているが、あとはゴツゴツと岩の突き出た浜が、海と道路にわずかな距離をつけているだけだった。
陽はもう沈んでいた。海峡をへだてた函館の灯は、この天気ではしばらく見ることができない。暗い夜の中を、ぼくは黙々と歩いていた。
塩風にさらされて、新雪はもうじとじとと融けかかり、ひどく歩きにくかった。県道といっても、夏は夏で砂埃が舞いあがるひどい道だ――本州のさいはてである下北半島の、さらに北端のこの地ともなれば、これは当然のことなのだろう。
こんな風土を呪ってもみたが、今はそんな気もなくなってしまった。たかが十七才であるというのに、ぼくは仏のように老いた心で、この道を夜になると通うのだった。
本町にある学校までは、歩いて三十分かかる。学校といっても、定時制の、しかも分校なのだから、独立した校舎があるわけでなく、中学校から間借りしたたった二つの教室で勉強をするのだ。全学年を合わせても四十名余りという少人数のために、一・二年で一教室、三、四年で一教室と、まとまって授業を受けているのだった。それでも校門には、青森県立なる名称を押し戴いて墨痕淋漓とした看板が掛けられてあり、それはもう一方の側に掛けられた中学校の看板と比べて、いささかも見劣りするものではなかった。
校舎の中は静まり返っていた。少し時間が早かったのだ。
暗い廊下をミシミシ軋ませて、ぼくは歩いて行った。そのはじっこの教室から、裸電球のあかりがうっすらと洩れている。誰か、もう先に来ているのだ。
「オス!」と言いながら、ぼくは片足で教室の戸をガラリと開けた。
教室では、たった一人、こちら側に背を向けてストーブにあたっている男がいた。ぼくの方を振り向きもせず、男は椅子の上でそっくり返りながら、天井に向かって煙草の煙を噴きあげていた。煙は悪びれずに、あたりに漂っている。
学生服を着たその男の頭髪が、油気のないバサバサな長髪であることは背後からでもわかった。一、二年を合わせて三十名足らず――その中の十名ほどの男の連中は、分校主任の訓示通り、みんな坊主頭であり、それでいて大人ぶりたく、こっそり煙草を喫っていたのだから、堂々と煙草をふかすこの長髪の男は、ぼくらの教室にふさわしくない人間だった。
何者だろうと、ぼくはストーブに近づいて行った。そして、見知らぬ服をちらちらとうかがいながら、ストーブを挾んで立っていた。
男は、ぼくを無視したまま煙草をふかし続けていたが、やがて、「君、何年?」と口を開いた。
ひどく歯切れのいい口調だった。北国の鈍重な方言の中で暮しているぼくにとって、彼のさわやかな発音は驚きだった。
「一年。」と、ぼくは答えた。
「ぼく二年。山田陽太郎っていうんだ。一緒にやることになるけど、よろしく頼むよ。」
彼はそう言うと、座ったまま後ろを振り向き、すぐそばの机の方に手をやった、そして椅子を片手で持ちあげると、ストーブ越しにそれをよこした。
「すわんなよ。」
ぼくは、流暢な彼の自己紹介にドギマギしながら椅子を取った。どうやっても太刀討ちできない自分の発音を思うと、こちらから名乗り返すことはできなかった。
ぼくが椅子に座ると、彼は服のポケットから無雑作に煙草の袋をつかみだし、ぼくにのべた。ゴールデンバットだった。
「喫わないかい?」
「いや、持ってる。」
そう答えてぼくがピースを取りだすと、彼は、「ぜいたくだな。」と、せせら笑うように言った。
ぼくはマッチを擦ってピースに火をつけた。そして、背を丸くして、掌で煙草をおおいかくしながら、漂い始める煙を気にしてチビチビと吸いだした。
彼の嘲笑は、またもや追い討ちをかけてきた。
「何だってそんな真似するんだい。こそこそやったって旨くないだろう。」
そう言うと、彼は最後の一服を思いきり吸い込み、ストーブの口にポイと吸殻を投げ捨てた。
カタン、カタンと、一歩一歩を確かめるような分校主任の足音が廊下にしたのはその時だった。ぼくは、あわてて煙草をストーブ台で揉み消し、ジャンバーのポケットにしまい込んだ。
たった今まで、彼が威勢よく噴きあげていた煙は、まだあたりに漂っている。窓越しにこちらを見た分校主任は戸を開けて入ってきた。
もう五十を過ぎ、白髪まじりの頭のくせに、洒落気だけはたっぷりとある男だ。濃紺の地に、グリーンのチェックが微かに浮きあがるダブルを着こなし、鉄のようにいかめしい顔で、彼は近づいてきた。
笑い顔を、ぼくはまだ見たことがない。もっとも、彼の顔に笑みというものをくっつけたら、ひどく釣合いのとれない結果になるだろう。その顔ときたら、天然痘か何か知らないが、噴火口のような穴だらけで、まったく汚ならしい。ぼくたちの間では、バフンと呼ばれていた。
「この煙は、誰のものかね。」と、バフンは気どった口調で言った。
「ぼくです。」と、即座に言葉を返したのは山田陽太郎だった。
バフンは、まゆをひそめて言った。
「君は何才だね。」
「十八才です。」
「煙草をのんでいいと思っとるのかね。」
「法律では許されていません。」
「君はどうおもってとるのかね。」
「いいことだと思ってはいませんが、悪いことだとも思いません。」
バフンは、いらだたしそうに身体をゆすりながら、「法律を守らぬ君は犯罪人だ。わからんかね、そんなことが……それに、長髪は好ましくないと、きのう、わたしが言ったはずだが……」と言った。
「長髪は、やっぱり法律に関係あるんですか。」と、すかさず山田陽太郎は言葉を返した。
「法律はすべてじゃない。」と、バフンは息苦しそうに答えた。
「その通りです。煙草だって、そんなに悪いことじゃありません。」
「馬鹿!」と、バフンは、とうとう堪えきれなくなって叫んだ。
「すみません。以後、気をつけます。」
陽太郎は、うやうやしく頭を下げて言った。
バフンは、くるりと背を向けると、せわしげに足を運んで教室を出て行った。その足には、いつものように黒いレインシューズがはかれていた。雪の粉がまだらについている。
「あの野郎の靴は何だい。土足で教室に入って来るなんて、人のことにケチをつけられる柄じゃないよ。あいつ、頭がおかしいんじゃないかい。」と、山田陽太郎はたまげた顔で言った。
「外国式にやってるつもりなんだべ。」
「雪だから汚れはしないだろうけど、一人で外国ぶったって、ここではピンとこないじゃないか。」
「……」
ぼくは黙っていた。さきほどからの山田陽太郎の行動は、バフンの言うことを上べではヘイヘイと守ってきたぼくら夜学生にとって、考えることのできない思いきったものである。陽太郎が正だとするなら、ぼくらは薄のろである。しかし、ぼくらが常人だとするならば、陽太郎は与太者なのだ。
彼の精悍な顔つきをながめながら、ぼくは下しようのない評価に戸惑っていた。
一人、二人と、やがて登校して来た連中が、ストーブの廻りにむらがっていった。
陽太郎は気さくに話しかけ話題を独占していた。どうやら彼は、東京のれっきとした昼間の高校からやって来た男であり、水産加工業を営むこの町の町議会議長の甥であるということが話の中味からわかってきた。
一時間目と二時間目は一般数学だった。担当はバフンだ。ぼくは中頃の席で、何となく山田陽太郎と並んでしまっていた。教室は固定していたが、座席は前を空けない限り、座りたい所に座ればよかったのだ。細かなバフンにしては自由なことをさせるようだが、これにはわけがある。遅刻や欠席がはなはだしく、座席を決めておこうものなら、あちらにポツン、こちらにポツンと、不入りであること一目瞭然のために、教師としては気合いがかからないからだ。
授業は、例のように面白くなかった。一人でしゃべりまくりながら、バフンは黒板に計算をしていく。これが高等学校というものかもしれないが、ここで勉強することが、ぼくの毎日の勤めにどれだけ役立っているかといえば、まったくなのだ。要するに、算盤をはじけて、ガリ版のコツをちょいと覚え、ゴマスリが巧みなら世の中に通用するのだから――
ぼくは、ポケットに突っ込んできたノートと鉛筆を取りだし、黒板の数式をうつしていった。何のことやらさっぱりわからぬ。いつもなら、バフンの汚ならしい顔を、それ以上は誇張できぬほど漫画にでも書いて暇をつぶすのだが、今日はそういうわけにはいかない。山田陽太郎と並んでいるというだけで、何だかバフンからにらまれているような気がするのだ。
ノートしながら、ちらと山田陽太郎を見ると、彼はまた、超然と腕を組んで黒板を見つめている。いやに余裕たっぷりだ。
――わかるのか――と、ノートのはしっこに書いて、ぼくは彼の脇腹をつついた。
彼は、ぼくのノートをヒョイとのぞくと、胸のポケットから取りだした万年筆で返答を書きつけた。
――わかってたまるか――
二人は顔を見合わせた。そして、ニヤッと笑いあった。ぼくの心にはまりきらなかった彼のある部分が、なぜかスッポリとはまっていくのをぼくは感じた。
三、四時間は物理だ。それで授業は終りになる。
物理は長井という先生が受持っていたが、ぼくらは、彼をオヤマと名づけていた。先生稼業は一年目の若い男で、ハンサムを通り越し、あまりに女性的な青っちろい顔をしている。なで肩で、声まで女のようにかん高い。
そのオヤマとバフンの二人が、ぼくらの分校のレギューラー教師で、ちっぽけなこの漁師町に住みついているのだ。バフンは数学の他に音楽、オヤマは物理の他に英語を教え、後の教科は、中学の教師がアルバイトをしている。
物理の授業は、数学よりも遙かに厄介だ。おそらく大学で使った教科書なのだろうが、手にした本をペラペラと読み、それをノートさせるのだ。チョークなど、ただの一度も握ったことがない。彼の朗読をどれだけ忠実にノートできたかということが、教室の中の自慢話のタネでもあったが、ぼくは始めから諦めている。そして、懸命にノートをしている連中にしろ、一種のゲームをしているだけなのだ。
山田陽太郎はといえば、鞄の中から取りだしたのだろうか、いつの間にかブ厚い本を机に置いて読みふけっていた。覗いてみると、小さな活字の中に、いやにデッカイ活字がゴツゴツとまじっている。逆さになったり、横になったりしている活字もあり、はなはだしい誤植のようだ。
「なんの本だ。」と、ぼくは囁いた。
彼は、本を閉じて表紙を見せた。〝日本現代詩大系〟と書いてあった。
「ダダの詩が載ってるんだ。」とつけ加えながら、彼はさっきのページを開き直した。
「ダダ?」と、ぼくは問い返した。ダダというのは、ぼくらの方言で親父のことを意味するものだったからだ。
「ダダイズムさ。」と、彼は言い直した。
「面白いか。」
「くだらんね。」と、彼はこともなげに言った。
翌日は授業はなかった。生徒会主催の弁論大会があるからだ。審査委員はバフンとオヤマ、それに本校から呼んだ教頭が加わり、町の助役が審査委員長だった。
八人の弁士の中の、ぼくも一人である。出たくて出るわけではない。生徒会主催などといっても、このための会議など一度も開かれなかった。大体、生徒会そのものが、何一つ活動をしていないのだ。弁論大会は、生徒会長の篠崎とバフンが勝手に計画したのだが、いざやる段になっても乗り気になるものはなく、ホームルーム委員が無理矢理ひっぱり出されることになった。ぼくは一年の委員長だったので、光栄ある弁士に選抜されたわけだ。
トップバッターはぼくだった。原稿は初めからない。
「諸君!」と言って一息入れると、山田陽太郎のニヤニヤした顔が目についた。
「我々は……」と次の言葉を言いかけたが、どうも後が出てこない。しゃべることは用意していたのだが、改まった言葉となると、どうもスラッと出てこないのだ。ぼくは方言丸出しでしゃべり出した。
人生論など読むべからず。人生は無意味なものだ。無意味だからといって嘆くな。無いということは丸裸になったみたいに、実にサッパリとして気分がいい。そのいい気分で死ぬまで生きよう――
そんな意味のことを呶鳴って終った。みんなはゲラゲラしながら聞いていた。ふざけたつもりはないのだが、方言というものは、こういう場所では喜劇的なのだろう。助役も笑っていたようだが、教師一同はひどく厳粛な顔だった。
ぼくの後に続く弁士達は、誰もかれも、よそゆきの言葉で終始した。弥次を飛ばすのは陽太郎だけだ。ぼくもやってやろうと思ったが、弁士席からでは失礼なので黙っていた。
クラーク先生の言葉が出てきたり、福沢諭吉が飛び出してきたりする。要するに、夜学生というハンディを乗り越えて頑張りましょう式の悲愴な訴えで終るのだ。
本音ではない。ぼく達はそんな悲愴がるほど、真面目に人生を考えて夜学に来ているわけではないのだ。何となくいいことがありそうだと入学したものの、どうせまともな高校には行けなかった人間なのだ。土方、杣夫、漁師、百姓、或いは平事務員や、オサンドンの身分が、たやすく変りそうもないと間もなく気づいて、さっさと止めていく者が多い。
ぼくらの学年は四十名が入学したのに、一年たとうとする今では十五名になってしまった。残った人間は、役にたたない勉強など止めて思いきり遊んでやれというふんぎりもつかない。虚勢(*去勢)された連中ばかりだ。暇をつぶすには、夜学は金がかからないからという、みみっちい根性の持主だといった方がいいだろう。
審査の結果は、一位が生徒会長の篠崎だった。大きな賞品を彼は手にしたが、ぼくは勿論、箸にも棒にもかからなかった。
終ってから、助役や教頭を囲んで茶話会がもたれた。ワラ半紙の上の駄菓子を宝物のようにいつまでも眺めながら、席はお通夜のようだ。
「くだらんね、帰るか。」と、山田陽太郎がぼくに囁いた。
「うん。」と、ぼくは返事をした。
ちょうどよく戸口のそばに座っていたぼくらは、駄菓子をこっそりとポケットに突っ込み、教室を抜けだした。
雪は降っていなかったが、外はかなり寒かった。白い息を吐きながら、ぼくらは早足で歩いた。
「君の演説よかったな。真実味がある。ぼくなら一位にしてやったのに。」と、山田陽太郎は歩きながらぼくをおだてた。
「サンキュー。」と、ぼくは嬉しくなって言った。
「でも、あの中味にぼくは反対だ。人生は無意味だなんて、ぼくは我慢できないよ。」
ぼくは言葉を返そうとして彼を見た。雪あかりの中で、彼の横顔はひどく淋しそうだった。ぼくは口をつぐんだまま彼と並んで行った。
その夜、ぼくは山田陽太郎に誘われて、彼が寐(*寝)とまりをしている水産加工場に行った。その加工場にある六畳一間の部屋で、彼は番人をしているのだった。
「今、火をたくからな。」
部屋に入ると、彼はストーブをいじりだした。ぼくは部屋の中に突っ立ったまま、ぐるりと廻りを見廻した。
柱時計が掛かっている。後は家具一つない殺風景なその部屋の出窓に、見慣れぬものが置いてあるのがすぐ目についた。
「ほう。」と、ぼくはそこに行って手に取った。
それは、埴輪だった。写真では見たことがあるが、実物は初めて目にする。左の小脇に太鼓を抱え、右手に握ったバチは、今正に、太鼓にふれる寸前のようである。その響きで死んだ魂を呼び戻そうと、死者のほとりに立っていただろうその埴輪は、特有のくりぬかれた目を虚ろにして、生を呼び戻すことの不可能であることを告げるようであった。
「無だな、この目は。」と、ぼくは言った。
「そうだ。無心だよ。」
「無心? 無心の無でねえ。虚無の無だじゃ。」
「とんでもない。虚無だなんて、そんな冒涜的な言い方は止めたまえ。」と、山田陽太郎はひどくむきになって言った。
「冒涜? 虚無がか? だって、そうだもの――世の中なんて虚無に決まってるでねえか。生きていたってどうっていうことねえ。」
「君の言うことはわかる。だけど、その虚無の無を、無心の無にカラリと晴らそうじゃないか。この埴輪の目がそうなんだよ。よく見てみな。埴輪の目は、決して虚無じゃない。無心に生を期待しているんだ――君はさっきの演説で、無いということはさっぱりすると言ったけど、そんな居直った言い方に反対するね。さっぱりするとかしないとか、そんな感情さえ意識しないような無心の無……」
「つまり、馬鹿になれって言うのか。」と、ぼくは喰らいついた。
彼は言葉につまったが、すぐに快活に言い返してきた。
「理屈のこねり合いはよそうや。とにかく、少しは毎日を楽しくしていこうじゃないか。とりあえず、学園の民主化に、少しは手をつけなきゃならない。あのバフンを何とかしなくちゃ駄目だ。」と、彼はもう覚えた分校主任のアダ名を持ちだして言葉を続けた。
「バフンとはピッタリだよ。君達も結構、レジスタンスの精神を持ってるじゃないか。それなのに、あのレインシューズを黙って見過したり、頭を丸坊主にしてるのはどういうわけなんだ。囚人じゃあるまいし。」
「おらたち、バフンの言うことに満足なんかしてねえ。おらたちみてえな、純然とした学生でもねえものは、煙草のんで、頭でものばして、ヘン、全日制の奴等、おめえたちのようなスネ囓りじゃねえんだ。立派な大人なんだって思わなかったらやりきれねえよ。けど、バフンは、おらたちが学生だって言う。三、四年にはそれほどうるさく言わんが、一、二年に向かってなら、実にうるさく頭のばすなって繰り返すんだ……おらたちが学生だなんて、とんでもねえことだ。クラブ活動もありゃしねえしよ。人が少ねえなら少ねえなりに、特別な親しみがあってもいいのに、一、二年の組と、三、四年の組はまるきり他人だ。挨拶さえもしねえんだから……みんな自分の殻に閉じ込もっていやがる。何かを変えていく気力なんてねえんだじゃ。」
「クラブ活動もないっていうけど、生徒会費は払ってるんだろう。何に使ってるんだ。」
「さあね、払うことは払ってるけど、使い道なんてさっぱりわからん。」
「よし、一発やろう。」と、山田陽太郎は突拍子もなく大きな声で言った。
ようやく燃えついたストーブの火が、豪華な音をたてていた。
「一発?」
「新聞部を作るんだ。バフンを叩き、みんなの眠っている声を呼びさまし、学園の民主化をかちとろうじゃないか。」
「駄目だ。声なんて元々ねえんだ。あっちの組と、こっちの組が他人だけなんでねえ。ストーブ囲んで漫談はやるけど、組の中だっててんでばらばらなんだ。みんな本質的なことを考えたり、話しあったりするのを避けている。」
「可能性はある。」と、山田陽太郎は断乎として言った。
「無い。」と、ぼくは意地になって言った。
「今日の弁論大会だ。」
「バカなっ――生徒会主催だなんてあんなものやりやがって、篠崎はバフンのロボットになって事を運んだまでだ。おかげでおらも員数集めに引っぱり出された。」
「ほう、洒落たことやると思ったけど、そうだったのか……だけど、ぼくが言いたいのは演説をしたっていうことだ。ともかく、借りものの思想でも、思想らしきものをしゃべったっていうことだ。それは、みんな何かを求めていることじゃないだろうか。心の底で、みんなキリキリと痛むものを持っていることじゃないだろうか。そこを足がかりにして、どえらい花を咲かせなきゃならない。」
その時、柱時計が鳴った。見上げると、針は九時を指していた。ぼくの帰りを待ちながら、今ごろ母は、ぼんやりと婦人雑誌をめくっているだろう……ふと、ぼくの胸に哀しみのようなものが漂っていた。
中学校を卒業し、この町から一時間ほど歩いた山の中にある鉱山に勤めるようになったころ、ぼくは毎日のように母を罵倒しては泣かせたものだった。
父は機帆船の船員だったが、ぼくが五才の時、海難事故で死んでしまった。婚家先きを出された母は、実家には戻れず、ぼくを連れて、旅館の住み込み女中になったのだ。
ぼくを全日制高校にあげることができなかった母は、ぼくの罵倒を浴びて泣いて謝まったものだった。許しを乞う母のちっぽけな姿を見ながら、ぼくはいつか自分の憤満(*憤懣)のやり場のなさに気づいていった。
ぼくは、次第にすべてを諦めるようになっていった。そして、ぼくが痛みを諦めていったように、夜学の一人一人の仲間も何かを諦めていったのだろうか。もし彼等の心の底に、山田陽太郎の言うような痛みがかくされているとしたなら、ぼくの心の底にも確かに痛みは消えていないのだ。そして事実、ぼくは妙に胸を締めつけられながら、母を思っていた。
「やろう。」と、ぼくは陽太郎に言った。
「本当か。」と、彼はぼくを見つめた。そして、ついと立ち上がると、出窓に近づいて行った。
彼は埴輪を取りあげると、しみじみ眺めているのだった。
新聞部発足のための運動は翌日から開始された。
ぼくらはまず、一、二年のぼくらの教室から仲間を見つけ、とにかく発足の声明を出してから、上級生を吸収していくことにした。
山田陽太郎の巧みな話術のおかげで、学校帰り、加工場に寄り道する者は、一人、二人と増えていった。一週間の内に、男女とりまぜ七名のガン首が揃ったのだ。
ぼくらは加工場の狹苦しい一室で、時のたつのも忘れ、恋愛を論じ、人生を論じあった。そして、今、新聞部が生まれようとしていることに興(*1)奮し、興奮のはてに疲れきったぼくらは、ごろごろとその場に寐転んだ。散会は午前零時を過ぎることしばしばであった。
七名の仲間が揃ったところで、ぼくらは大まかな計画をたてた。新聞の名称は、山田陽太郎の提案に従い〝暁鐘〟と名づけることにした。編集長は彼、ぼくがガリを切り、印刷にかかる経費は生徒会に要求することになった。
そこまで決めた日の翌日、ぼくと山田陽太郎の二人は学校に出ると、休み時間、廊下を通りかかった生徒会長の篠崎をつかまえ、このことを伝えた。
篠崎は聞き終ると、困惑したような表情で、「今、返事できねえして、明日まで待ってくれねべか。」と言った。
「なぜだ。」と、山田陽太郎は問いつめた。
「青木先生に聞いてみねえば……」と、篠崎はバフンの名を出した。
「バフンに? 笑談はよせよ。生徒会の役員で話し合うっていうならうなずいてもいいけど、バフンとは何だ。生徒会はバフンのものか。」
カンカンカーンと、その時、鐘が鳴った。授業が始まるのだ。
鐘の係は、オヤマだ。職員室の前の、廊下の天井からブランと鐘が下がっている。その紐を引っ張って鐘を鳴らし終ると、オヤマはこちらに歩いて来た。
仕方なく、ぼくらは篠崎から離れた。
放課後、ぼくらは篠崎をつかまえ、たっぷり話し合おうとしたが、彼の姿は見えなかった。誰もいなくなった校舎の中で、職員室のあかりだけがついている。
こっそり覗くと、バフンと篠崎が何やら話し合っていた。
翌日、ぼくら二人は、一時間目が終ると篠崎に呼ばれた。
廊下に出ると、彼はつくろった微笑みを浮かべて言った。
「きのうのことだけど……あれ、諦めてくれねべか。」
「なぜだ。」と、ぼくも陽太郎も期せずして言葉を返した。
「予算が出せねえんだ。」
「どこに使ってるんだ。それをはっきりとさせろ。それで納得ついたら、金はぼくたちで負担する。」と、山田陽太郎はきつく言った。
「ちょっ、ちょっと待って……」
篠崎は、あわてて自分の教室へ入って行ったが、すぐに、金銭出納簿を手にして出て来た。ぼくらはそれをめくった。
四月、五月、六月……と、一円の支出もない。そして、二月、つまり今月になって、突如として支出が連続しているのだ。
みんな、弁論大会に使った金である。賞状、賞品、反省会茶菓子代などに三千円ほど使っている。それでもまだ、三千円ほどの金は残っていた。
「なんだこれ――弁論大会なんてやりたくてやったわけでもないものに、こんな金使うのか。もっと、みんなが本当に楽しめるもののために使わせろよ。」と、山田陽太郎は言った。
「だって、月に十円の会費で何できる? 後は、卒業式のサヨナラパーテーで使うつもりだけど、そんなことより他に使い道ねえんだもの……」と、篠崎は弁解した。
「十円じゃ安いに決まってる。値上げすりゃいいんだ。みんなのために使われる金なら、文句言う奴はいないさ。会長なら会長らしく、どんどん計画をたてて、みんなを引きずっていくくらいの力を見せてくれたらどうだい。」と、陽太郎は負けていない。
篠崎は黙ってしまった。
「バフンが許可しなかったんだべ。」と、ぼくは言った。
篠崎は、やはり黙っていた。
ぼくは腹立たしくなって、「バフンの所さ行くべ。」と、陽太郎の腕を引っ張った。
だが、彼は、「待て。」と、ぼくを引っ張り返して、教室へ戻ろうとするのだった。
ぼくは、口をとがらして彼に従った。
教室に戻ると、新聞部のメンバーは、待っていましたとばかりに寄って来た。陽太郎は教室の中央に座ると、手短に結果を報告した。そして言った。
「いいか、明日、全校生徒の前でバフンと対決するんだ。この問題は、みんなのものにしなくちゃ駄目なんだ。」
「ウオーッ。」と、ぼくらは叫び声を上げた。
いつの間にか廻りに寄って来て、陽太郎の話に聞き入っていた新聞部以外の連中も、手を叩いて喝采した。
だが、たった一人、ぼくらのむらがりから離れてストーブにあたっている男がいた。それは、二年のホームルーム委員長をしている島宗だった。彼は、篠崎と同じ勤め先きの役場で給仕をやっているのだが、腰巾着のような男なのだ。
放課後、彼が篠崎と連れ立って、こそこそと職員室に入って行く姿をぼくは見た。
翌日は土曜日だった。月曜と土曜は授業前に講堂に集まり、バフンの訓話を聞くことになっている。
その日、彼は、何やらブ厚い綴りを手にして壇上に上った。
「気をつけえっ――礼。」と、篠崎は、いつもやっている号令をかけた。
礼が終った途端、山田陽太郎は大きな声で叫んだ。
「質問! ぼくらが新聞部を作ることについて、生徒会長からどんな話がありましたか。」
バフンはあわてたふうもなく、手にした綴りを開いた。
「エーッ、生徒会は生徒のものだから、生徒の自由になるなどという考え方をしている者が、みんなの中にいるようです。一昨日、山田君達が新聞部を作りたい意向を持っているということを、生徒会長から聞きましたが、慎重に考慮した結果、その活動は学生としての本務を逸脱する危険性があるという判断で、生徒会長を通して再考を促すように伝えました……それは、生徒の自主性を尊重して、問題を、生徒の手に返したのです……しかし、ここで是非、言っておきたいことは、わたし達教師は、生徒会の運営に最終的な責任を持っているということです。ここに、県の教育委員会より、生徒会活動に関する通達が来ているので、読み上げます。」
バフンは、綴りを持った手をピーンと突き出し、教育勅語を読むような不動の姿勢で朗読し始めた。
難しい言葉がやたらに出てくる。御名御璽で終ってもおかしくない堂々たる文面だった。その意味は半分と理解できない。
朗々とやり終ると、バフンはほっと息をついて姿勢を崩した。
「何だかよくわからないけど、理由なく許可するなとは言ってないようですね。学生としての本務を逸脱するなんて抽象的です。それに、そんなことは、今、初めて聞きました。生徒会長は、予算がないからと言っただけです――とにかく、駄目なら駄目で、理由をもっと具体的に言ってくださいっ!」と、陽太郎は叫んだ。
「それは、君の胸に聞いてみればわかることだっ!」と、バフンは、かなり興奮してきた。
「理由はこれだっ!」と、山田陽太郎は、つかつか前へ出て行った。そして、バフンの足が相変らずはいているレインシューズを指さした。
陽太郎は、ぼくらの方を振り向いた。
「諸君、この靴を見てください。学校の中にこの格構(*格好)で入っているのは、この青木先生だけです。こういう道理をわきまえない自分が、新聞で叩かれるのが恐しくて、新聞部を許可しないのに違いありません……」
「田舎者! 大学ではこれが普通だっ!」と、バフンはすっかり怒りだし、とんでもないことを言った。
「ぼくは、江戸っ子です。そして、郷に入れば郷に従えという言葉も知っています。だから、ぼくはこの通り、上靴をはいています……でも、郷に入っても、従えないこともあります……それは、沈黙をするということです。」
そこまで言うと、山田陽太郎は、再び生徒に呼びかけた。
「三、四年の諸君、ぼくらは新聞部を作ることを計画しました。勿論、あなた方にも仲間になっていただきたいのです。いくら夜学生だからといって、暇がないからといって、クラブ活動もやれないなんて、あんまりカサカサ乾き過ぎていると思います。ぼくらには、青春というものがあります。授業の中に埋没ばかりしていないで、ぼくらの心をぶつけ合い、高め合うための時を持とうじゃありませんか。そのさきがけとして計画した新聞部を、青木先生は正当な理由もなく許してくれないんです。これは、ファッショでなくして何でしょう。ぼくらはこの弾圧をはね返し、学園の民主化をかちとらなければなりません!」
「そうだっ! そうだっ!」と、谺した叫び声は、残念ながら、手はず通りに相づちを打った新聞部員だけの声だった。石のように口をつぐんだ顔達の中で、叫び声はひけ目を感じていた。
バフンは蒼白な顔になり、ブルブルと身体を震わしながら、壇上から飛び降りた。
「待ってください。」と、陽太郎は言った。
その声が聞こえないかのように、「篠崎君、来なさい。」と、バフンは言うと、足早に講堂を出て行った。
篠崎は、ヘコヘコと後をついて行った。
石の顔達は急にざわめき始めた。思わぬ珍事で授業は流れそうだ。愉快でたまらないといった表情である。
「教室に入って待っていてください。」
オヤマがひきつった声でそう言うと、バフンの後を追って行った。
授業は一時間つぶれただけだった。二時間目の始まる頃、篠崎が現われ、ホームルーム委員長である、ぼくと島宗を廊下に呼びだして言った。
「新聞部だけでなく、もっといろんなクラブ作って、本格的なクラブ活動をやることにするから……新しいクラブ作りたい者は、名称と活動内容を、おらさ報告するようにみんなさ伝えてくれねべか……」
その夜、ぼくら新聞部員は意気洋々と学校を出た。
ふと、振り返れば、夜の中に横たわる二階建ての校舎には、まだ掃除の後始末をしているのだろう――片隅の二つの教室に暗いあかりがついている……しかし、ぼくには、そのあかりが、目映いほど痛く感じられるのだった。
ぼくらは例によって、加工場へ足を向けた。
すっかり興奮をしてしまい、これからの活動についてワイワイとしゃべり合うのだが、山田陽太郎は浮かぬ顔つきで、一向に話に加わって来なかった。出窓に腰を掛けて、あの埴輪をぼんやり見つめているのだ。
「大将、どうした。」と、ぼくは声を掛けた。
「うん、残念でね。」
「残念?」
「結局、篠崎とバフンがことを決めたんじゃないか。それに、ぼくがあれだけアジッたのに、ここにいるメンバーの他は、少しもあの場で反応を示してくれなかった……」
「くよくよするな。とにかく、クラブ活動は始まるんでねえか。」と、ぼくはこともなげに言った。
「そうだ。そうだ。」と、たちまち相づちが彼をくるんだ。
ぼくらは、加工場のすみっこから魚臭い板きれを見つけて来て、投書箱を作ることにした。
〝暁鐘〟と、墨で書かれたその投書箱は、毎日、加工場と学校を往復した。間借りの学校では、そのまま廊下に掛けておくと、中学生にいたずらをされてしまうだろうという配慮もあったが、加工場の集まりの中でその箱を開け、その中味をみんなで味わうことによって、ぼくらは集まりをますます愉快なものにしたかった。
しかし、投書は少なかった。日に一通か二通、感傷的な詩や短歌が、詠み人知らずのまま、ほうり込まれているだけなのだ。
そうは言っても、学校の空気は悲観的とは言えなかった。卓球、舞踊、演劇、手芸、それに篠崎が音頭をとる弁論の五つのクラブも発足の準備を始め、休み時間、教室の片隅にむらがりながら相談しあっている姿が見えるようになった。二日、三日とたつ内に、みんなの登校時間は次第に早くなり、授業前に集まるグループも出てきた。
クラブ代表の話し合いも持たれた。もう二月なのだから、来年度早々、運営費について検討することにし、それまでの費用は自腹を切ることになった。
週に一回、授業時間をクラブ活動に振りかえることもバフンは許した。
気に喰わないことはと言えば、オヤマが顧問という名目で、しつこく新聞部の進展状況をたずねることだった。
新しいメンバーが一人として加入しないことも気にかかった。
バフンとの対決から一週間たったころだった。登校の道で、ぼくは島宗と一緒になった。
歩きながら、彼はぼくに言った。
「暁鐘っていうのは、どこかの町にある共産党の文学雑誌と同じ名前だって、青木先生が言ってたそうだぞ……山田陽太郎ってのは共産党でねえのか? 町会議長の紐つきだから、先生も遠慮してるようだけど、山田には気をつけた方がいくねえかなあ……ああいう、町のボスの身内なんてのは、その反逆で共産党になるものが多いようだからな。太宰だって、そうだったんだべ……でも、山田は所詮、貴族様だ。おらたちのような労働者でねえ。のんびりと留守番やってて、暇つぶしをしてるんだからな……みんな、あいつのことを敬遠してるんだ……老婆心ながら、君の耳に入れとくよ……」
ぼくの心の中は、まるで、かみそりが走ったような感触を受けていた。共産党といえば、つい一、二年前に、新聞やラジオで盛んに報道された火炎瓶と結びつく、恐ろしい存在だったからだ。
ぼくは、むっつりとして足早になった。島宗は、どんどん後ろになっていった。
その日、学校が終ってから、相も変らず続いていた加工場での例会は、この話をめぐって終始した。
新聞の名称を変えるか変えないかで、ずいぶん揉めたが、結局は、意地になっても〝暁鐘〟で貫き通すことに決定した。しかし、共産党と同一視されるのは心外だということで、みんなの意見は一致していた。
あの対決の日以来、どうも活気が足りなくなった陽太郎は、殆ど話に加わらず、何かを考え込んでいた。
島宗の話が腹立たしく、その中味の一切をぶちまけてしまっていたぼくは、陽太郎を中傷した事実だけは黙っていた方がよかったなあと後悔するのだった。
山田陽太郎が、ぼくらに挨拶もなく学校を止めたのは、その二日後のことだった。
どこかへ飛び出して行ったのだという噂だったが、彼の行先きは誰も知らなかった。
加工場での例会が絶たれると共に、まるで足を失ったように新聞を出す意欲は一人一人の胸で倒れていった。一号を出すこともなく、新聞部は自然消滅した。
新聞部だけではない。せっかく出来たいくつかのクラブも右へならえをしてしまったのだ。
何一つ、夜学は、変らなかったのだ。変ったことといえば、バフンが、レインシューズを、スリッパにはき代えるようになったことだけだった。
2
落書きや居眠りで、相変らずのつまらぬ講義を過しながら、ぼくはいつの間にか定時制を卒業していった。
卒業したものの、そのことは、ぼくの生活に何等の恩恵ももたらさなかった。十人そこそこの事務室しか特にない鉱山事務所で、ぼくは倉庫の管理を殆んど一人の責任でやっていたのだが、ぼくの身分はどこまでも坑外夫であった。
鉱山の本社は東京にあり、各地に鉱業所を持っていた。毎年、春になると、大学を出たての社員がぼくらの鉱山にも入って来ては、いつか本社勤めになったり、他の鉱山の係長などに栄転をして行く……
組合はあったが、御用組合だった。年に一度、山神祭の日になると、社長は東京からやって来て、神社の広場で家族主義を唱えた。
配られた折り詰めと二合瓶で、坑夫達は酔って歌った。ぼくもその中の一人だった。
やたらに酒ばかり飲み、マージャンで夜を明かし、あげくのはて、ぼくは血を吐いた。肺結核だった。
ぼくは母と離れて、遠い青森市の郊外にある療養所に入った。
そこまで行かなくても、同じ下北の地の中にも療養所はあった。しかし、ぼくはふるさとから離れたかったのだ。ぼくの人生に吹きつける津軽海峡の塩風を、ぼくは呪っていたのだろう。
県内ではあったが、ぼくの入った療養所の患者達は聞きなれぬなまりで会話をしていた。話はわかるが、ぼくは、明らかにヨソ者であった。
半月ほどたって、個室から大部屋に移った時のことである。
「下北って、猿や熊が今でもいるんだってなあ。」と、同室の木下という男が話しかけてきたものだ。
茶化すような言い方に、ぼくは腹が立った。猿や熊など、ぼくは一度も見たことがない。出るには出るようだが、それはかなり奥に入った、ほんの一部の地域でのことなのだ。しかし、そんな誤解をされても当然なほどの僻地であることは、疑うことのない事実である。ぼくは、心の中で重たく黙りながら、さりげない微笑で彼の言葉をはぐらかしていた。
木下は、療養所にある患者自治会の会長をしていた。小まめに走り廻っては、療養所の当局といろいろな交渉をして、給食の献立や、重症患者の附添いなどについての改善を、多少なりとも成し遂げていた。人の話では共産党員だということであり、彼もまた、それを吹聴していた。
患者自治会は、日本患者同盟と称するものの末端組織でもあった。国立療養所の特別会計制度反対、健康保険法改悪反対など、いろいろな署名や、それらの記事を載せた機関紙が、しげしげと病室を回覧されていた。
新米は一度はやる義務があるとのことで、ぼくは大部屋に移ると間もなく、部屋代表というものに無理矢理祭りあげられた。
初めて出席した部屋代表会議は、生活保護法の基準額の低さを訴えた岡山の療養所の朝日茂という人へのカンパについての相談だった。
木下は患者の名簿を見ながら、一人一人の拠出額を頭から決めていった。部屋代表は、自分の部屋の連中の、割り当てられた額を集金するだけのことなのだ。
「下北、おまえ、生活保護じゃないから百円だ。」と、ぼくの査定も難なく決まった。
下北というのは、この療養所でのぼくの姓だった。石塚というれっきとした姓があるのに、ぼくは下北で通るようになっていた。名付け親は、木下である。
初めは抵抗を感じたものの、いつの間にかその姓に慣れ、ぼくは療養所に根をおろしていった。
三年たち、健康保険が切れた。病気は一向によくならず、ぼくは生活保護法による患者になった。
母は、旅館の女中をとうに止めていた。ぼくが結核のためである。客を扱う商売だから、結核が家族にいるのはまずいと言って、追いだされてしまったのだ。
母は、間借りの部屋を探したが、なにしろ田舎町のことだ。結核を同じように恐れて、誰も相手にしてはくれなかった。親戚さえも、誰一人、手を差しのべてくれなかったのだ。
母は自力で奔走した。そして、古びた木造建ての避病院の一室を、管理人という名目で借り受けることになった。
管理人といっても、その代償を貰えるわけではない。家賃がただというだけのことなのだ。母は、失業対策の人夫に出て働くようになった。
健康保険が切れてから、母の働きと共に、療養所からの請求書の額は増えていった。生活保護法は適用されていても、基準額を超えた収入はみんな医療費に廻さねばならなかったのだ。ニコヨンの僅かな収入の中から払えるはずはなく、医療費の滞納は増えていった。
医者は、空洞のあるぼくの肺を切除することを勧めたが、ぼくはその気になれなかった。生きようとする気力が、どうしても起きてこなかったのだ。
虚しさのあまり、ぼくは病舎の中でいくつかの恋をした。そしてぼくは、松林の陽の陰りの下で恋人を抱きしめながら、漂ってくる女の体臭に淋しくなり、枝葉の間の空の青さにぼんやりするのだった。
人を恋う心と、厭う心に引き裂かれながら、ぼくは日々を過していた。
山田陽太郎の消息を知ったのは、そんなある日である。
隣のベット(*ママ)の療友から新聞を借りて開いてみると、思いもかけず、彼がそこにいたのだ。
写真の彼は、漁師が着る仕事着のような形をしたものを広げて手に持っていた。唐草模様に似た大柄な模様で白く染め抜かれたその着衣は、記事によるとアイヌのもので、アツシという名称なのだそうだ。
三面のトップに組まれたその記事で、彼は考古学研究者ということになっていた。遺跡を尋ねて歩く内、下北半島の各地の旧家にアツシが伝わっていることに興味を抱き、それを片はしから買い取って歩いたのだそうだ。
はからずも、それは蝦夷と呼ばれた東北の祖先と、北海道のアイヌとの関係を考察する上での貴重な資料であるということが、中央の学者の目にとまったというようなことが書かれてあった。
なつかしさのあまり、ぼくは彼に手紙を書いた。下北の脇野沢という村にいることだけは、新聞を読んでわかったからだ。
彼からの返事は仲々(*中々)来なかった。人恋しさのあまり手紙を書いてしまった自分が嫌になり、ぼくは澱んだ心で、相変らずの日々を過していた。
半月後の四月、彼は突然、ぼくを尋ねて来た。
看護婦が面会人の来ていることを告げた時、ぼくは首をかしげた。二ヶ月に一度、母が来る以外に、ここへ訪問する者などあるはずがなかったからだ。そして、母ならば、看護婦を通さなくても、まっすぐ病室へやって来るはずなのだ。
面会室を覗くと誰もいなかった。
「ヨオッ!」と、玄関から声がして、ぼくはそちらを振り向いた。作業服を着た山田陽太郎が外に立っていた。ちょっと離れた所に一台のダットサンがとまり、中には誰かがいた。
「しばらくだなあ。」と、ぼくはスリッパのまま外へ出た。
彼は、ポケットから煙草を取り出した。ゴールデンバットだった。
「まだ、これのんでるんだじゃ。」
いつの間にか身につけた方言でなまらせながら、彼はそう言うと、自分で一本を取り、ぼくに袋を差し出した。ぼくも、一本を取った。
煙草はひどく旨かった。ここ一週間、一文の金もなく、ぼくは母の送ってくれる月に千円の小遣いを待ちわびていたのだ。
ぼくらは、黙って煙草をのみあった。何からしゃべっていいのか、ぼくにはわからなかった。おそらく、彼もそうだったのだろう。
「ブ、ブー」と、助手席にいた男が警笛を鳴らした。
「おれの主人だ。青森に用事あって来たんだ……また、その内、会うことがあるかもしれねえな……早く、元気になれじゃ……」
彼はそう言うと、ぼくの手に、口を切ったゴールデンバットを押しつけた。
「これ、置いてく。」
さりげなく言い放つと、彼は運転席に入って行った。
雪どけの坂道を、泥をはねらせて下って行くダットサンの後姿を、ぼくは涙をにじませ見送っていた。
こわれものであるかのように、ゴールデンバットは両の掌でやわらかに抱えられていた。確かに、彼の残していったささやかな善意は、卵のようにこわれ安いものかもしれない。しかし、ぼくはその善意の卵から何かを孵しはじめていたのだ。
その夜、消灯後の暗いベットで、彼の残していったゴールデンバットを味わいながら、ぼくは好江との関係を固めようと決意していた。
そのころ、ぼくは療養所に来て六度目の恋をしていた。好江がその相手だった。
彼女は、ぼくの病棟の看護婦であったが、エキゾチックな目をした彼女がこの療養所に来たのは、一年前の春のことだった。
北海道から来たという彼女をめぐって、患者達は興味を込めて話し合ったものだ。なぜなら、療養所の看護婦はみなすべて県内の出身であり、わざわざ海を越えて、あまり変りばえのしないであろうこの土地にやって来るということはおかしなことであったからだ。
失恋をして逃避して来たのではないかということが、ぼくら患者の一致した憶測であった。そういえば、無口で、ほとんど笑いというものを見せたことがない彼女の彫りの深い顔には、悲しい陰影が刻まれているようであった。
「あれは、メノコだじゃ。」と、物知り顔で言うのは木下であった。
「メノコ?」と別な声がかかると、北海道に旅行をしたことがあるという木下は、得々とメノコの講義をした。
消灯後の寐つかれぬひととき、ぼくら同室の八人は布団にくるまりながら、彼女がメノコであるかないなということについて議論をしたものだ。
「絶対、メノコだじゃ。あの目がそうだ。あんなエキゾチックな目をした看護婦は、ほかにいねえば?」と、木下は力説する。
「メノコってば、アツシとかいうもの着るんでねえか。」と、ぼくは、ついその頃、新聞で見た陽太郎の写真を思いだして言った。
「そうそう、アツシっていうデッカな模様つけた着物を着てな、頭さ鉢巻きしてるんだじゃ。その格構(*格好)で踊りおどってたぞ。」
「イヨマンテか。」
「いや、イヨマンテは、あいにくやってなかった。でも、年柄年中おどってるんだじゃ……熊のしゃれこうべはあったぞ。木のまたに差して、萱ぶきの家の前さ置いてあった。」
「肉はどうしたんだべ。」
「喰ったのよ。熊の肉喰って生きてるんだ。」
誰彼となく問いかける言葉に、木下は自信たっぷりの答えを聞かせていた。
「大崎がアイヌなら、何だって熊の肉を喰えない所さ来たんだべ。いくら失恋したからって、北海道は広いもの、行く所は一杯あったべえな。」と、話はまた好江のことにうつっていった。
「そう言えば、この前、詰所で牛乳を飲んでたぞ。アイヌが牛乳飲むべか。」
木下は、ちょっと返答が出来なかったが、「純粋のアイヌでねえんだ。血が混じってるんだ。混ざりメノコなんだ。」と、どうやらこうやら結論を下した。
「混ざりメノコか。」と、ぼくらは苦肉の造語に爆笑した。
日がたつにつれて、好江についてのおしゃべりはぼくらの間で少くなり、やがて消滅していった。単調な生活の中で話題に飢えていたぼく達が彼女をまな板に上げただけのことで、さしたる興味は元々なかったからだ。
その中の一人であったぼくが、彼女を一人の女性として意識するようになったのは、初雪が療養所をくるんだ日のことだった。
夜半から降り出したボタ雪は、その日の朝になってものっとりと降り続けていた。窓ぎわに寐ていたぼくは、ぼんやりと雪の空を見上げていた。
いつの間にか、自分自身が空へ向かって飛翔して行くような錯覚にとらわれ、ぼくは限りない昇天を続けていた。昇っても、昇っても空は遠く、ぼくの心は、立ち込める悲しみの中に漂うのだった。
無意味な時の浪費の中で心を冷やされながら、ぼくは一ヶ月ほど前、療養所を半治りのまま退院して行った五人目の恋人のことを思っていた。
手紙は来なかったし、ぼくも出そうとはしなかった。ぼくらは、今日の傷口をなめ合うための口づけが必要であっただけなのだ。内へ内へとなめ合いながら、どうしようもない心の深淵を覗き合ってしまった頃、彼女は経済的な事情で退院をして行ったのだ。
ぼくは、たとえ半治りではあってもシャバへ出て行った彼女を思い出している自分に気づき、ぼく自身の心の底に澱んでいるシャバへの欲望を感じていた。
そして、シャバは、今、ぼくが吸い込まれていった、遠い空ではない。丘の下に連なり見える家々の屋根にゆらめく、ストーブの煙がそうではないか――なぜ、ぼくは遠い世界に逃避しようとするのだろう。なぜ、間近かなシャバに戻って行こうとしないのだろう……
ぼくの心に首をもたげた生の欲望は、心の中で葛藤を続けながら、雪だるまのように太っていった。
雪は、昼も近くなるとようやく止んで、空はカラリと晴れ渡った。ぼくは、枕もとの床に置いた長靴の埃を払って、展望台へ出かけた。そこから見える下北半島をしのびたくなったからだ。
展望台には先客がいた。好江だった。
ベンチは、雪のために座ることが出来ない。好江もぼくも、そこに立ったまま、眼下に広がる陸奥湾に目をやっていた。その彼方に横たわるのは下北半島であり、それを越えたさらに向こうに、好江のふるさとはあるのだ。
下北の淡い姿を見ていると、ぼくはまた、生きることに憂欝になった。
鉱山はつぶれてしまっていたし、帰ったところで職はない。そればかりではない――母の身を置く部屋さえも与えなかった人々の住むふるさとが、ぼくに生を鼓舞するはずはなかった。
「北海道は、見えねえな……」と、ぼくは、うらやむように彼女に言った。
いきなり声を掛けられて彼女は戸惑ったようだったが、「残念だわ……」と、小さな声で呟やいた(*ママ)。
「残念? そうかな……憎らしいだけでねえか? だから、北海道からここ迄、来たんでねえのか? それにしても、北海道も青森も大した違いねえんだべ? 冷たい雪は降るしよ……どうせなら、東京さでも行けばよかったのに……」
ぼくがそう言うと、彼女は相変らず海の彼方を見つめたまま、「東京には、雪がないもの……」と答えるのだった。
「雪? 雪がいいなら、北海道の方がいいべさ。青森なんかより、うんと雪あるべ。」
「ふるさとから離れたかったのよ。それでいて離れきれず、わたしは雪のあるこの土地へ来たんだわ。きっと……」
そう答える彼女の、白いセーターのふくよかな隆起を、ぼくは、ぼく自身のものであるかのような親しみを込めて、横目に感じていた。その胸の下で葛藤するふるさとへの愛と呪いは、そのままぼく自身の心に通じるものであったからだ。
その日以来、ぼくは、彼女が夜勤をやった翌日になると、展望台へ足を運ぶようになった。非番になった彼女が、同じ場所に来ないだろうかという期待があったからだ。そして、ぼくの期待はしばしば叶えられるのだった。
二人はいつの間にか、思い出を語り合う仲になっていった。
貧乏で学用品もろくに買って貰えなかったこと。子守りに雇われてしばしば学校を休まねばならなかったこと。補助金やアルバイトでやりくりしながら準(*准)看護婦養成所を出たこと。旭川の療養所に勤めながら定時制高校を卒業し、それを契機に、かねてからの計画通り北海道を去ったこと……
それらの思い出を、彼女は言葉少なに語った。言葉を選ぶようにぼつぼつと語る彼女の話しぶりは、ぼくの心を打った。めあてもなく通して来たぼくの青春に引きかえ、ふるさととの訣別一途に生き抜いて来た彼女の青春が、ぼくには目映いものに感じられた。
ぼくは彼女に値する人間なのだろうか? そんな自問にとらわれて、ぼくは人知れず頭を抱えるのだった。自分が嫌になり、ぼくは、ぼくらの間に芽生えつつあった何ものかを進行させようとしなかった。
3
山田陽太郎が置いていったささやかな土産――一袋のゴールデンバットは、ぼくに翼を与えるきっかけとなった。彼が訪ねてきた翌日、ぼくは好江を展望台に呼び出したのだ。
その日、朝から勤務していた彼女が検温のため廻って来た時、ぼくは薬包紙に時間と場所を書いて押しつけた。
夜になるのは、ひどく長かった。やがて六時が近くなった頃、ぼくは病舎を脱け出した。
展望台が近づくにつれ、激しい海風がぼくの皮膚を次第に強く叩いていった。長かった冬の季節を一掃するかのような勢いであった。
ぼくを待つ彼女の白いセーターが夜目の中で見えた時、張り詰めたぼくの胸の中で動悸は高鳴った。
ぼくは、それを静めようと、彼女に横顔を見せたまま、見えない夜の海に目をやった。波の音だけが足元で轟き、海の存在を数えていた。
彼女もぼくと並んで、同じように目をやっていた。二人とも、言葉はなかった。
「風邪をひくわよ……こんな夜、何の用事?」と、やがて、ふるえる声で彼女は言った。
「……」
「風邪をひくわよ。」
「ひいてもいいんだ。」と、ぼくは、火照る心をかくすようにさりげなく言った。
「バカ!」
好江は、突然、低く、だが喉元から込みあげるように叫ぶと、くるりと背を向けて駈け出した。反射的に、ぼくの足も地を蹴っていた。
たちまち、ぼくは彼女に追いつき、腕をつかまえた。二人はもつれながら、まだ雪の残る道ばたに倒れた。粗い、氷のような雪が、手の甲を擦った。突き刺さるような、しかし、爽やかな感触だった。
その年の秋、ぼくは肺葉切除術を受けた。そして、再び春が訪れる頃、ぼくは社会復帰のための相談を好江と繰り返していた。
たとえ職はあっても、下北に戻る気のなかったぼくは、何とかして、明かるい(*ママ)都会の風景の中で暮らす道を考えたかった。ぼくは、バスで三十分ほどの青森市内へ出かけ、職業安定所へ出向いた。しかし、まだ療養所にいる身体では、まったく相手にされなかった。
その頃、県内の患者自治会の連合体では、アフターケアーを作らせようという運動を起こしていた。退院を間近かにして、戻って行く職場のない連中を収容し、手職を身につけさせるという施設なのだが、木下の呼びかけに従って、十名ほどの陳情団がぼくらの療養所から出て行ったことがある。
陳情団といえば威勢がよいが、街の空気を味わえることが、最も嬉しいような連中の集まりであった。勿論、ぼくもその一人である。
ぼくらは、肺病たかりのやる政治運動の力を信じてはいなかったし、その必要がある者も少なかった。ぼくや、木下のように、療養所に根を下した(*ママ)者は数えるほどしかいなく、いつの間にか普及した新薬を使っては、元の職場にさっさと帰っていく連中が多かったからだ。ただし、一年もすると、再び舞い戻って来ては、いつの間にか職場を締め出されて悲鳴を上げる者が多かった。しかし、所詮、自治会は、つき合い上の止むを得ぬ組織に過ぎなかったのだ。
県内各地の療養所の陳情団が合流して、やっとこすっとこ県の民生部長に会ったものの、「何しろ、予算が……」の一言で、アフターケアーの問題は片づいてしまった。
県庁内の一室で絶叫する木下ら、数名の幹部を除いては、ぼくらに憤りは起きてもこなかった。なるようにしかならないのだ。組織なんてちゃんちゃらおかしい。とにかく、自分の力で戦わねばと、ぼくと好江は相談の末、思いきって、青森市に下宿を探すことにした。
五月のある日、ぼくは外出許可をとって、彼女と二人で市内を歩き廻り、やっと、六千円の下宿屋を探し出した。
二日後、そこをねぐらにしての職探しは始まった。下宿屋には、職業を適当にごまかし、弁当持参で出かけるのだ。
二週間たって、ぼくはようやく筆耕の道を見つけた。鉱山の事務所にいた頃、鉄筆を握った経験はあるのだが、プロとなると並大抵のことではなかった。一ヶ月二ヶ月とたって、技術はどうやら向上していったものの、収入は見合ったものではなかった。それに、急ぎの仕事が多い関係上、夜業や徹夜は普通のことであり、自分の体力を考えて仕事の量を押さえなければならなかった。
月に一万円の稼ぎが限度だった。母を呼びよせ、好江と暮らすのだというぼくの願いは、いつになったら叶えられるのか、まったく見当もつかなかった。
好江は休みのたびに、ぼくの下宿へやって来た。ぼくは疲れた目をはらして鉄筆を走らせながら、彼女と、言葉少くとりとめのないことを話すのだった。
たまに、ぼくの休日が彼女の休日とかち合っても、ぼくはもう外へ出る気力もなく、南向きのむんむんと空気が漂う裏二階の下宿部屋で駄菓子を噛り合うのだった。
ぼくらは、結婚についてふれることを避け合っていた。それを口にすることは、ぼくらの心を一層悲しくすることだったからだ。
追いつめられた生活を、さらに不愉快にするような来訪者が来たのは、七月のある夜のことであった。
「今晩はアーーお宅に、石塚っていう人いますかア!」
玄関先きの大きな声が二階にも届いて、ぼくは下宿の内儀さんが呼ぶより先に、階段を降りて行った。声の主が木下であることは、姿を見なくてもわかった。
「ヨオー、下北!」と、ぼくを見るなり彼は言った。かなり酔っているようだった。
「ここが、よくわかったな。」と、ぼくは、さしたる仲でもなかった彼の訪問を不審に思いながら言った。
「君の彼女から聞いてきたんだ……おれな、今日、退院したんだ。明日から洋服屋の外交でメシを喰うことにしたんだじゃ……その祝いに街で一杯やったけど、どうも一人じゃつまらねえ。つき合ってくれねべか。」と、彼は、ぼくの腕を引張った。
二日以内に仕上げねばならない仕事をその日持って来ていたぼくは、澁い顔で答えた。
「今、忙しいんだけどなあ……」
「商売繁盛していいな。景気いいところで、おれの人生の出発を祝ってけろじゃ。」と、木下は強引にぼくの腕をつかんで離さない。
仕方なく、ぼくは彼につき合うことにした。
どん底のぼくの生活にひきかえ、街のあかりはあまりにも豪華だ。人々の足どりは快活である。
「健康だ! 実に健康的だ!」と、木下はさかんに喝采をしながら、よろよろ歩く。
「肺病あがりの人間の生活なんて、誰も彼も無視していやがる。患者運動なんて、少しも世の中につながってねえべ?」と、ぼくは木下に言ってやった。
「そう思うか? そう思うか?」と、彼はぼくに抱きついて、頬をすりよせた。
気がつくと、朝だった。ぼくは、下宿の部屋で木下と寐ていた。口がひどく乾き、頭が痛い。
目をつぶって昨夜のことを思い出すと、次第に記憶がはっきりとしてきた。
飲むほどに、酔うほどに、欝積した悩みが爆発し、破れかぶれになったぼくは、どこまでもぼくを連れ廻す木下について、かなりのハシゴをかけたのだ……
木下が、もそもそと体を動かして起きた。
ぼくの顔を見ると、照れくさそうに笑い、「煙草ないか?」と言った。
ぼくは、枕もとに脱ぎすてた服のポケットから、煙草を取って彼にやった。
一服をつけ終わると、彼は、「さあ、帰るかな……」と呟やいた。
「そうか……」
「さあ、帰るかな……」と、また彼は呟やいた。そして、「おれ、煙草銭ねえんだけどなあ……」と、呟やきを続けるのだった。物欲しそうな言い方だった。
ぼくは財布を開いた。四千円はあった金が、たった二百円しか残っていなかった。ぼくは、むしゃくしゃした心で、百円札を一枚、彼に突きつけた。
「同志、下北! これが共産主義だ。」と、木下は傲然と札を取った。
それ以来、彼はしげしげと訪ねて来るようになった。家は、市内にあるのだそうだ。そして、彼が来るたび、ぼくの仕事の予定は狂い、経済状態は危なくなった。 二日酔いの頭に鉢巻きをして、徹夜仕事を増やしながら期日に間に合わせるのだが、その月の月末、ぼくは下宿代を好江に助けてもらった。
二ヶ月ほどたった頃から、木下はどうしたことか、姿を見せなくなった。
理由は、すぐにわかった。店の金を持ち出して、東京へ飛んだのだそうだ。彼の来歴を調べに警察が療養所にも来たので、好江がそのことをぼくに教えてくれた。
党の仲間が心配して、いろいろ奔走したのだが、とうとう彼は檻に入れられたということも、好江からまた聞きした。
ぼくは、ほっとした心になるのだった。
4
九月の晴れたある日、朝からやって来た好江に、ぼくは、突然、汽車に乗ることを提案した。ちょうど仕事がなかった時だったので、気晴らしに、初めての二人の旅をやってみたくなったからだ。
見知らぬ土地でありさえすれば、行き先きはどこでもよかった。ぼくらは、駅の料金表を眺めながら陽気にしゃべり合い、日帰りに都合の良い土地を選び出した。目的地は、鰺ヶ沢に決まった。
鰺ヶ沢は、津軽平野を縫った汽車が日本海に出たところにある、ひなびた漁村である。砂浜の上では、明日の漁を待ってちっぽけな漁船がたむろしていた。ぼくらは砂を踏みしめながら、どこまでも歩いて行った。
しばらく行くと、あたりには岩礁が多くなってきた。空はからりと晴れているのに、海は荒れている。
二人は歩き疲れてその場に腰を下ろし、波に叩きつけられる岩礁の姿を黙って見つめていた。見つめる内に、その岩礁は、ぼくら自身の存在のように思えてくるのだった。
ぼくは不貞腐れたように、ごろりと背を砂に倒した。荒れた海とはうらはらにまっ青な空が、ぼくの目に沁みた。
こんな明るい空の下で、なぜ、ぼくらは痛めつけられねばならないのだろう。何とかして、ガリ切りの生活から足を洗い、安定した職が欲しい。でも、どうせ学歴もないこのぼくは、今の商売にあまんじるより他はないのだ。これで結婚なんて出来るだろうか……共稼ぎでやっていけば、暮らしてはいけるだろう。でも彼女の両親は、こんな生活力のないぼくを、きっと嘲るに違いないのだ……
ぼくの心は、しめっぽくなっていた。同じ思いだったのだろう――好江のしゃくりあげる声がした。
ぼくは、成すすべもなく、寐転び続けていた。
突然、好江は、ぼくの胸に身体を倒して、赤児のように大声を上げて泣き出した。
「わたし、もう二十五なの……二十五なのよ……」
泣き声の合い間にはさまる切れ切れの言葉が、ぼくの胸をふるわせた。
「結婚するべ。」と、ぼくは彼女を強く抱いた。
帰りの汽車の中で、ぼくらはそのための相談をしあった。結婚式を挙げる金もなければ、結納を届ける金もなかったが、一たん心に決めてしまうと、そんなことは屁の河童だった。向かいの席の見知らぬ親父さん達を気にしながら、ぼくらは低い声で語り合っては、嬉しさに堪えきれなくなって笑いをたてたりもするのだった。
「せめて、挨拶をしに北海道さ行きたいな。」
「いいんだ。どうせわたし、黙ってこっちへ来たんだから、勘当されてるみたいなんだも……それより、あなたのおかあさんの所に、二人で行かない? 見てみたいなあ……あなたが育った所……」
「親戚が煩わしくてな。いざという時には役に立たんくせに、結構、口出しをしたがるからな……お袋には手紙を出して来て貰うさ。三人でお祝いするべ……でも、あんたのとうさんさも、手紙は書かなきゃならんべな……」
ぼくがそう言うと、好江は頑強に、「全然、わたしの家のことなんか心配しないで……手紙を出すなら、わたしが出すわ。本当に、いいんだから。」と言うのだった。
父も母も喜んでいたということを、それから間もなく、ぼくは彼女の口から聞いた。
木造建てのアパートの一室を借り受けた。ぼくらの結婚式が開かれたのは一ヶ月後だった。
その日、ぼくらは二人で、母を駅に出迎えに行った。突然の知らせに驚いた母は、ただおどおどと好江に頭を下げていたが、アパートに着いて、料理を作りだす段になると、ああだこうだと言い合いながら、好江と一緒に浮きうきと動き廻るのだった。
もうしばらくと言うぼくらの言葉を振り払って、母は翌朝、早々に戻って行った。
まだ五十を過ぎたばかりだが、母の足取りは、都会のさっそうとした人混みの中では、ひどく危なかしく見える。
ぼくらは、ホームの中までついて行った。
「かあさん、すまねな……」
発車のベルが鳴りだした時、ぼくは心にあったことをようやく言っていた。
「何が?」
「かあさんを、一人にして置いて……」
「バカこげ――おまえなんか、あてにしてね。」
母は、笑い飛ばすように言った。
ガクンと汽車は動き出した。ぼくの心にも、ガクンと響く決意があった。
――きっと、母をよびよせよう――
汽車の姿が見えなくなり、ぼくと好江は陸橋の階段を昇って行った。
「失業対策の人夫だなんて、大変だわ……何とかよびよせない?」と、好江は言ってくれた。
「ありがとう。でも、そうなれば部屋だって二間いるしな……今の所だって、やっと見つけて四千円だろう……」と、ぼくは心にかかることを言っていた。
療養所にも、五万円ほどの滞納があって、督促状が送られてきていた。経済事情は、並大抵ではなかったのだ。
「大丈夫だわ。二人で働いているんだもの、切りつめてやれば――」と、好江はこともなげに言った。
ぼくは、母に手紙を出した。返事はすぐに来た。
今すぐには行かない。結婚早々で、いろいろ揃えるものもあるだろうから、今行っては迷惑をかけるばかりだ。でも、一年もたったら、世話になるために行くかもしれない――
そういう母の返事に対して、ぼくはほっとした気持になるのでもあった。
やがて、好江は市内の市立病院に口をみつけ、そこで働くようになった。療養所に通勤をするよりはよかったし、何よりも、彼女の同僚にあらたまった結婚の挨拶をしなかったことで気まずくなっていたことが、大きな理由だった。
看護婦という職業も、ガリ版屋と似たものである。週に二日か、三日は夜勤があり、翌朝、彼女が戻って来ると、徹夜仕事を終えたぼくと一緒に、昏々と眠ってしまうというようなことはしばしばであった。
ぼくらが、ゆったりとした心で話し合える時間は、実に乏しかった。
師走の月に入って間もないある日のことだった。
例によって昼も過ぎた頃、二人はのこのこと起き出し食事をとった。
食事が終って、茶をすすり合っていると、好江が低い声で言った。
「わたし、赤ちゃんが出来たわ……」
「……」
「前から、そうじゃないかと思ってたんだけど、二ヶ月なんだって……」
「診てもらったのか?」
「ええ。」
「そうか……」と、ぼくは活気のない呟やきを返した。
家族が一人増えることは、それだけ経済的な負担が重くなることであり、母をよぶことがますます困難になることだったからだ。
好江も、ぼくの心を察していた。
「おかあさんをよべなくなるわね。」
「いいさ、お袋はまだ元気なんだから。」と、ぼくは笑って打ち消そうとしたが、笑いはぎこちなかった。
「産んでもいい?」
「おろせとは言えんべ。」と、ぼくは本心をぶちまけてしまった。
彼女はツンと立ち上がって、茶椀を片づけはじめた。
祝福されるべき命の芽生えを、このような形で認めねばならぬことが、ぼくにはひどく侘びしかった。仕事に明け暮れる生活の流れの中で、新婚早々の気分が次第に色あせていたぼくと好江は、その日以来、さらに重たい気分になっていくのだった。
5
一ヶ月ばかりたった日の朝だった。
出勤の準備をしていた好江より一足先きに出て、昨夜製版を終えた原紙を届けに行って帰って来ると、好江はまだ部屋にいた。いつの間にか外出着にきかえて、スーツケースに何やら詰め込んでいるのだ。
「どこさ行く?!」と、ぼくは驚いて言った。
「北海道……すぐ帰って来るから……」
「北海道? 何しに?」
「……」
「理由を言え、理由を!」と、ぼくは声を荒くした。
彼女は、財布の中からたたんだ紙を出すと、黙ってぼくに手渡した。
ぼくは、せっかちにそれを開いた。電報だった。
――ソボ キトクスグ コイ――』チチ
「いつ届いたんだ。」と、ぼくはいぶかしくたずねた。
「あんたが出て行った、すぐ後……」
「何も、かくすことねえ――いくらおれが、しがない下請けの職人だからって、徹夜仕事の四、五回もやれば、旅費の分は稼げるんだ。一人で長旅をして、腹の子どもにもしものことあったらどうする――おれも、一緒に行くぞ。」
「行ってもらいたくない理由があるの。」と、彼女は、急にあらたまった顔になって膝を折った。
「理由?」
「どうしてもと言うなら、言わなくちゃならないけど、後悔するわ、きっと……」
「言ってみな、後悔なんかしないよ。」と、ぼくは妙にやさしい口調でうながした。
彼女は、じっとぼくを見つめた。そして、ふと目を落として呟やいた。
「わたし、アイヌなのよ。」
「……」
「隠していて、ごめんなさい……でも、そのことをあんたが知ったら、わたし、あんたと結婚できなくなっちゃうと思って……」
ぼくの頭の中では、いつかの木下の、言葉のはしはしが狂い舞っていた――アツシ、メノコ踊り、熊のしゃれこうべ……
「それがどうしたんだ。」と、ぼくは、心の中のひそかな舞いを吹き飛ばすように言った。
木下のような男の言葉に振り廻されるなんて、我慢のならないことだった。
彼女は、淋しそうに笑って言った。
「あんたに、ついて行ってもらいたいと思う心も、あるのよ。アイヌが、同じ人間だっていうことを、わかってもらうために……」
「同じ人間だよ。同じ人間だよ。おれも一緒に行くよ。」
ぼくは彼女の肩をつかんで、激しくゆさぶった。
好江の身体にさしたる変調もなく、ふるさとである日高国の一寒村に着いたのは翌朝だった。
熊のしゃれこうべはどこにもなく、アツシを着た人間は一人もいない。山間の雪をかぶった僅かな田畑の中に、小じんまりと身を寄せ合うその部落は、青森のどの地にも見られる貧しい村の風景と変りはなかった。
祖母はもう息をひきとり、葬儀の準備は整っていた。休む間もなく、ぼくらは葬儀に参列した。
すべては、仏式でやられた。出棺の時が来て、最後の対面に人々が顔を乗り出した時、ぼくも好江に従って初めの対面をした。
激しい号泣の声で棺は囲まれていた。赤裸な感情で使者を送る人々のむらがりの中で、ぼくは目頭を熱くしていた。
物言わぬ唇の廻りに、青黒くしみ込んだ入墨が、ぼくの目に鈍くうつっていた。そのくすんだ色彩は、一人の人間の重たい生涯を象徴するかのように痛々しかった。
焼場から帰ると、人々はまた好江の家に寄り集まった。
焼酎瓶を立てながら、とりとめもない四方山話をしていた人々は、酔いが廻ってくると、奥の間にいたぼくと好江を座の中央に引張りだした。そして、「ムコ様、よろしくお願いします。」と口々に言いながら、彼等は、ぼくに焼酎を勧めるのだった。
あけすけな人々の勧めにのって、ぼくは、かなりそれを飲んだ。
目がさめると、部屋は静かだった。いつの間にか酔いつぶれてしまった内に、みんなは帰ってしまったのだ。
背中が冷え冷えとしていた。うすべりも敷かずに剥き出した板の隙間から、風が吹き上がってくるのだ。
こわごわとした木綿の丹前を払いのけ、ぼくは起き上がった。大きなくしゃみが出た。
「北海道は、寒いんでしょう。」と言いながら、好江の母は、ストーブに薪をくべ足した。
ランプの灯が、うっすらと室内を照らしている。終戦直後の電気事情が悪かった頃、停電に備えてランプなどを用意したものだったが、今時ランプとは珍らしい。
ぼくがランプを見上げていると、好江の父が言った。
「ダム工事が、この奥でさかんにやられていましてね、わしも働きに行ってるんですが、二つ出来る内の一つの発電所はもう出来てしまいました。でも、そこで作った電気は、わしらの頭の上を通り抜けていってるんですよ。苫小牧あたりの工場に、流れていくんでしょうねえ……この部落に電燈をつけるには、一戸当り五万円の負担金がいるっていうんですから、まったくバカにしてますよ……」
静かな語り口の中に込められた怒りをじりじりと感じながら、ぼくは葬儀のあわただしさからとき放たれた家族の人々と、ようやく落ちついて対面をするのだった。これまで、ほとんど家族のことをしゃべらなかった好江なので、ぼくは、その時はじめて、ストーブを囲んで座る好江の母親についてくわしく知ったのだった。
好江は末娘であり、兄が二人、姉が一人いた。みなそれぞれ結婚をして、夫婦ともども葬儀に集まったのだ。
長兄の他は、この部落から出て生活しているようであり、久々に顔を揃えたとのことだった。
「婆さんも、とうとう死んでしまった。これで、この村には入墨(シヌエ)をした者は一人もいなくなってしまった。悲しんでいいのか……喜んでいいのか……」と、父は誰に言うともなく言った。
「何だって、あんなものをしたんだべ――馬鹿なっ!」と、吐き出すように言ったのは長兄だった。
「そう言えば、おまえらにその話をしたことはなかったな……わしが若い頃のことだ。わしは、わしを産んだ婆さんを恨んでさんざん毒づいた……〝アイヌなんかに生まれたくなかった。よくも恥しくなく、そんな入墨(シヌエ)だなんてものをしたんだ。わたしはアイヌでございますって、わざわざ和人(シャモ)に見せたかったのか〟――そう言って、婆さんに喰ってかかったことがある……婆さんは、泣きながらわしに言ったよ……〝したくてしたもんでねえ〟ってな……おまえはもうメノコになったんだ。和人(シャモ)にいたずらされてもいいのか。入墨(シヌエ)をしてしまえば、和人(シャモ)は気味悪がって近づいて来ないんだ。アイヌの血を汚されてたまるかって、威されたり、なだめられたりしながら、娘だった婆さんは入墨(シヌエ)をやられたんだそうだ……かみそりで刻まれ、白樺の煤を擦り込まれた時の痛さに泣き叫び、二十日たっても、唇の廻りは腫れ上がったままだったそうだ……〝この入墨(シヌエ)さえなかったら、どこか遠くへ行ってしまいたい。このおかげで、一生、アイヌで過さねばならん〟って、婆さんは、逆にわしに口説いたんだ……」
「そんな婆さんでも、村の年寄りが死ねば、アイヌ風(プリ)の葬式のさいはい振りに出て行ったでねえか……」と、長兄は納得できぬ表情で言った。
「そうよなあ……でも、そんなもんでねえかなあ……」
父はそう言うと、ふと好江の方に顔を向けた。
好江の声が、ぼくの耳元で響いた。
「もう二度と、こんな所に来るものかと思っていたのに、やっぱり来てしまったわ……わたしね、離れていても、お婆さんからちっちゃいころ聞いた、オキクルミ神(カムイ)のことを思い出すの……オキクルミ神(カムイ)から授かった毒(ブシ)矢の威力をいいことにして、アイヌは座ったままで矢を放ち、獲物をたらふく喰べては、ただごろごろとするようになった。だから、オキクルミは、アイヌが堕落したって、怒って天上へ行っちゃったそうだけど、でも、今、わたし達が貧乏をして和人(シャモ)に軽蔑されるのは、決してわたし達のせいじゃない。和人(シャモ)が悪いんだって、わたしは物心ついた時、お婆さんに心の中で反発してたわ……でも、このごろ思うの……何でもかんでも人のせいにしないで、思いきり自分の力を出していかなきゃならないんだって……そしたら、やっぱりオキクルミの話は本当かもしれないって思えてきて、お婆さんがなつかしくなってくるの……」
「おまえは、婆さんに可愛いがられたからなあ……心配して死んだよ。生きてる内に、立派なムコさんを見せたかった。」と、母は目をしばたたかせて好江に言った。
「おまえはおとなしかったけど、意地があったからなあ……苦労してでも看護婦になっていいムコさんを見つけたが、みんながみんな、そううまくはいくもんでねえ……苦しまなくてもすむ苦しみは、味わいたくねえもんだ。」と、長兄は相変らずうなずこうとしない。
父が、その言葉を受けついでぼくに言った。
「あなたは内地の方だから、よくおわかりにならんでしょうが、わしらは北海道に渡って来た和人(シャモ)のために――和人(シャモ)なんて言い方をして気を悪くしないでください……アイヌだ、和人(シャモ)だといっても、純血のアイヌなんて一人もいやしません。和人(シャモ)にだまされたりして、みんな大なり小なりの血は混じっているんです。でも、和人(シャモ)は今でも、わしらをアイヌ呼ばわりします。だったら、やっぱりわしらも、和人(シャモ)という言葉を使わなきゃ、話の説明が出来ないんですよ――和人(シャモ)には、ひどい差別を受けたものなんですよ。開拓々々で、和人(シャモ)がプラウで馬耕している時、わしの爺さん達は、鹿の角で葦の原野を拓いたんですからねえ……そうして拓いた土地も、結局は貧乏のために、年貢なし、期限なしの小作地として和人(シャモ)に借りとられていきました。わしらアイヌの土地は旧土人保護法っていうもので勝手な売買は禁じられていましたから、名前だけはわしらのものだったんです。でも、戦争に負けて、民主主義になったら、農地改革なんてものをやりやがって、わしら名前だけの地主から、土地は正真正銘、和人(シャモ)の手にうつってしまいました。土地も学歴も金もないわしらは、造材人夫や土方仕事で、この身体を切り売りするよりほか、喰っていく道はないんです。」
「差別は、今だって生きているのよ。アイヌ、アイヌって、学校でも馬鹿にされたわ……北海道にいる限り、わたしは一生、和人(シャモ)の差別を受けていかなきゃならないと思ったら、どうしてもここを脱け出したくなったのよ……準看護婦の養成所に入ろうと心に決めて、先生に話した時、先生は言ったわ……おまえ、看護婦になるのかっ! さも、ふさわしくないという口ぶりで、そう言ったの……わたし、差別を憎むからこそ、差別を抱いてはならない職業を選んだのよ。わたしには、ふさわしいものだったんだわ……」
好江がしみじみ言うと、長兄はやけな口調で言葉を吐いた。
「とにかく、アイヌ風(プリ)の葬式を出せる婆さんは死んでしまった。やろうたってやれる人はなし、南無阿弥陀仏で葬式をやられて、婆さんはどう思ってるか知らんが、芽出度いことだ。」
「アイヌ風(プリ)が消えて、差別が消えるもんならなあ……」と、父はため息をついた。
重苦しい沈黙が、あたりに漂っていた。ぼくは、そっと、そこにいる親族の顔を見廻した。
どの顔も、深い血の縁で結ばれたように、彫りの深い悲しみが刻まれていた。そして好江も、明きらか(*ママ)にその一人だった。ぼくは、ぼく一人が異邦人であることを思い知らされ、言い知れぬ孤独に落ち入っていった。
青森に帰った夜、母がやって来た。
まだ旅の姿もとかないでいたぼくらを見て、母は、「どこさ行って来た? 腹の子どもを大事にしねえばねえ時なのに……」と、驚いて言った。
ぼくは、重たい口調で、好江の祖母の死を告げた。
「ちっとも知らねえで、失礼してしまったのう……遠い所、悲しみ抱えて大変だったべ……」と、母は好江に語りかけた。
「……」
「北海道っていっても、南の方だから、思ったほど遠くねんだ。」と、ぼくは好江に代って母に言った。
「そう言えば、日高とかいう方だったのう……日高って言えば、おら方の町からも、随分、出稼ぎが行ってるぞ、何でも、ダムの工事だとかって……」
「そうかい。」と、ぼくは、その因縁に驚いていた。
沿岸漁業は不振であり、農業といってもたかがしれている――数多くの出稼ぎ人が北海道へも行っているということは、かねがね耳にしていたことだった。
しかし、母の言葉をあらためて聞く時、ぼくの心の中では、ふと、貧困にうちひしがれているふるさとの姿と、あの部落(コタン)の姿が二重に重なっていた。
アイヌ呼ばわりをされる部落(コタン)の人々――そして、下北呼ばわりをされたこともあるぼく――この偏見と、貧困は、ぼくと好江をつなぐ共通の母胎ではないだろうか……
そんな重いが胸をかすめもしたが、あの葬儀を終えた夜の重苦しい沈黙を考えると、好江とぼくの、風土の違いを感じてしまうのだった。
ぼくも所詮は、下北の冷たい風土と絶縁することは出来ないのだろうか。ぼくが結ばれねばならなかったのは好江ではなく、津軽海峡の冷たい潮風を同じように浴びながら、人生に突き出されていった女性なのではなかったろうか――そんな思いにとらわれたぼくは、なかなかその感情をふっきることが出来なくなっていた。
ぼくの口は、日々に重くなり、内へ内へと込もっていった。好江もまた、ひどく無口になるのだった。
6
臨月は近くなっていった。
好江は、予定日の一週間前まで勤務していた。
産前産後、それぞれ三週間の休みがとれることを法律は定めていたが、なかなか法律の通りにいかないのが今の世の中である。
そんな病院に対して、彼女は不平も言わなかった。白衣の天使の精神は、たっぷりと好江にあり、彼女はうまい具合に働かせられるのだ。
陣痛が訪れたのは、予定日より十日も遅れた朝だった。
とうの前から手伝いに来ていた母は、すっかりしびれを切らしていたが、好江が痛みを訴えると、「ハイヤー呼んでこいっ!」と、生き生きした声でぼくに指図した。
かねてから予約をしていた病院に、好江は身体を移した。
陣痛は、なかなか本格的にならなかった。時おり、小刻みに襲ってくる痛みのため、彼女が油汗を出してうめくと、母は彼女の背中に手を差し入れながら、一生懸命にさすってやった。
「ほうれ、こうすれば楽だべ……まだまだ、このくらいの痛みなら生まれねんだ……それ、もっと痛め、もっと痛め……」と、おどけたように声をかけながら背中をさする母に、好江は歯を喰いしばりながら、笑いを浮かべていた。
産室に入ったのは、夜の九時頃だった。ぼくは、産室の前の廊下で足踏みをしながら、時おり様子を見に病室からやって来る母に首を振るのだった。
十時を過ぎた頃、不意に、耳慣れぬ泣き声がした。ぼくは、腕の時計を見た。針は、十二分を指していた。
ゆっくりと病室へ向かったぼくは、母に誕生を告げた。
間もなく、手押車に座って好江が産室を出てきた。
「女の子だって――」
そう言う好江は、明かるい表情だった。
彼女がベットに戻ってややたつと、産着にくるまった赤ん坊が、看護婦に抱かれてやって来た。
「さあ、御対面ですよ。」と差しのべられた赤ん坊を、ぼくは、そっと受けとった。
頬から目にかけて、歌舞伎役者のように桜色の色どりがあったが、雪のように肌の白い赤ん坊だった。そして、その子は、まるでぼくが見えるかのように、あどけなく目を開いていた。
「あれまあ、もう目を開いて!」と、たまげたように母が言った。
どこかで、見たことのある目だ――と、ぼくは思った。
その目を思い出せぬまま、一年は過ぎた。
赤ん坊は、晶子と名づけた。結晶の晶である。愛の、結晶であることを、ぼくら自身にどうしても言い聞かせたかったのだ。
ぼくは相変らずガリ切りをやりながら、晶子のミルクや、おしめの世話をしていた。
無理をしてでも稼ぎまくり、母をよびよせるならば、母に子守りを頼むことは出来た。しかし、月に一度は晶子の御気嫌(*機嫌)伺いに出て来る母にそのことを言うと、相変らず耳をかさなかった。
「病気した身体だ。無理しちゃならん……栄養もとらなきゃならんし、金がかからんようにした方がいいんだ……どうせ、家で仕事してるんだから、晶子のお守りだって出来るべ? なあに、まだまだ、わしは大丈夫だい……」
依怙地な母の心をそこなわぬように、ぼくはそのことにふれなくなっていた。
晶子の世話をぼくがするということは、ぼくにとってかえって救いであった。いそいそと帰宅しては晶子をあやす好江ともども、ぼくらは、晶子に没入することのみによって、心の底のじっとりとした沈殿物はそのままに、辛くも結ばれていた。そんなぼくらを、母は気づかなかった。
7
初誕生が過ぎた夏のある日、ぼくは晶子を抱いて散歩に出て行った。
この頃、とみに、わけのわからぬ言葉をしゃべり出すようになった晶子は、市内を流れる自動車を見て、すっかり御気嫌になり、「アブブー、アブブー……」とさえずっては、道行く人をほほえませた。
おもちゃを買ってやろうと、玩具店に足を向けていると、ぼくは、後ろから肩を叩かれた。
「やあ。」と、ぼくは驚いて言った。
叩いた主は、山田陽太郎だったからだ。
「今、そこの本屋で本をあさってて、ひょいと道路の方を見たら、君が行くじゃないか――驚いたなあ……もう、すっかり治ったんだか。」
「うん、おかげさんで元気になった。御無沙汰してたなあ。」
「おらの方こそ、失礼してたよ。」と、あれ以来、一度も音信をかわし合わなかった二人は、互いに同じことを言った。
「君、市内にいるのか?」
「うん。そっちは?」
「小湊。」と、彼は答えた。
小湊といえば、青森駅から汽車で四十分ほどの所である。
「ほう、小湊か。」と、そんな近くに彼がいたことに、ぼくは嬉しくなっていた。
陽太郎は、晶子の顔を覗き込んだ。
「この子、君の娘か?」
「うん、この前、誕生をすぎたばかりだ。」
「そうか、おらは、まだチョンガーだじゃ。」
快活にそう言うと、陽太郎は、晶子を頬を(*ママ)軽くつついて、「この子の目、どこかで見たことがあるなあ。」と言うのだった。
「君もか、おらも前からそう思ってたけど、思い出せねえんだじゃ。」
「さあて……どこで見たべなあ……」
彼は、ちょっと首をかしげたが、話を変えて、「おら、明日から、県立図書館でアイヌの民俗資料を展示することになったんだじゃ。ひまなら、見に来てくれねえか。」と言った。
「アイヌ?!」と言葉を返しながら、ぼくは、〝そうだ。こいつは、アツシとかを集めていたんだっけな。〟と思い出し、奇妙な気持になっていた。
「じゃあ、準備があるから、これで失敬するぞ。」
そう言うと、彼は、もう人混みの中に、さっそうと肩をなびかせて歩いていた。
翌日、ぼくは再び、晶子を抱いて県立図書館に出かけた。
三回の展示室の前には机が置かれて、山田陽太郎はかっぷくのいい二、三人の人々と談笑していた。
ぼくは、ガリ版風情で過している自分の現実に劣等感を感じて、彼に気づかれぬよう、すっと展示室の中に入って行った。
ガラス張りのケースの中には、いろいろなものが展示してあった。
アツシにも、黒っぽいものや、白っぽいものなど、様々な種類があるものだ。鮭の皮や、鹿の毛皮で作った履物だとか、そりの豊かな刀剣もあった。
「ホッ、ホッ。」と、驚嘆するように叫びながら、晶子は、ぼくの腕の中で身体をゆさぶり、それらの品々を指さした。
確かに、これは珍らしい品物なのだ。これは過去の物であり、アイヌの現実の生活とは何等の関わりもないのだから……そう思った時、ぼくの心には怒りが込み上げていた。
一体、山田陽太郎は何のためにこれを集め、人の目にさらすのだろう。蝦夷とアイヌの関係を示唆する貴重な資料かもしれないが、蝦夷とアイヌが同じ血族であることが証明されたところで何になるのだろう。純血のアイヌはもういないと、好江の父は語ったが、それでもぼくは、血の断絶を感じとってきてしまったではないか。二十世紀の現実に於いて、なお差別を引きずっていく彼等の悲しみを、ショーウィンドウのような、この展示会場で物語ることは出来ないのだ――
ぼくは、晶子を抱いて、その場をつかつかと出た。
山田陽太郎は、まだ歓談を続けている。
ちらっと、彼がこちらを見たようだった。
「おいっ! おいっ!」と、ぼくを呼ぶ声を背中に捨てて、ぼくは飛ぶように階段を降りた。
好江が帰って来たのは五時だった。
「ちょっと、出て行ってくるから。」と、待ちかねていたぼくは言った。
「どこに?」
「ちょっとだ。」
言葉を濁して、ぼくは図書館へ向かった。あれから家へ帰って気を落ちつかせている内に、ぼくはどうしても、山田陽太郎と二人きりで話をしたくなっていたのだ。
展示会場は開いていたが、彼はもういなかった。ぼくは、そのまま駅へ足を向けた。
駅前の広場には人だかりがあった。参議院選挙が近づいていたのだ。
候補者が、かすれた声を張り上げている。他人事のように、ぼくはそこをすり抜けて行った。
いつの間にか三十才になってしまったぼくの人生は、相変らず貧乏であくせくとしているではないか。何一つ変りはしないのだ。政治なんて、まったく他人事としか思えないのが、ぼくのいつわらざる気持であった。
小湊駅に着いた時、あたりは薄暗くなっていた。下りの時刻板を見ると、終列車まで二時間足らずの時間しかない。
田舎町ではあるが、結構大きな町のようだ。来るには来たものの、どこに彼が住んでいるのか見当もつかないぼくは、駅の前でしばらく思案にくれていた。
雨が降り出してきた。せっかく来たのだからと、ぼくは郵便局に彼の住所を問い合わせることを思いついて、赤電話をかけた。
うまい具合に、住家はわかった。ぼくは、教えてもらった道筋を頭の中に叩き込むと、駅前から真直ぐにのびている道を、雨に濡れながら小走りに歩き出した。
小さな繁華街を通り抜け、首尾よく、町のすみっこに彼の下宿屋は見つかった。しかし、彼は留守だった。
「青森から昼過ぎに帰って来たけど、どこさ行ったべ?」
下宿屋のおばさんは首をかしげたが、「今、電話してみるから……」と、奥に引込んで行った。
間もなく、おばさんは出て来た。そして、気の毒そうな顔で、「山田さんの勤めてるハイヤー会社さ電話したけど、今日は、一日休みとっていないんだそうですよ。」と言った。
雨は、風をともなって次第に激しくなってきた。ぼくは、雨足がゆるくなるのを待とうとして、玄関先を貸してくれるように頼んだ。
おばさんは、中に入って休むように勧めてくれた。ぼくは、山田陽太郎を待つことにした。
彼は、なかなか帰って来なかった。
一時間近くたって、すっかりしびれを切らした頃、玄関の戸が開く音がした。
障子のガラス越しに、かがんでそちらを見たおばさんは、「あっ、来た、来た。」と、ぼくに言った。
ぼくは急いで玄関に出て行った。
傘も持たずに、ずぶ濡れになった山田陽太郎がそこにいた。
彼は、驚いたようにぼくを見た。そして、「上れよ。」と、ひどくぶっきら棒に言うと、さっさと二階へ昇って行くのだった。
何だか、様子がおかしかった。ぼくはいぶかしく思いながら、彼の後をついて行った。
彼はふすまを開けた。一歩足を踏み入れて、ぼくはしばらくその場に立ったまま、部屋の中を眺めていた。
見事に復原された、へその高さほどもある土器が、ずらりと部屋を囲んで並んでいるのだ。
石油ストーブに火をつけると、彼は、それをまたぎながらあたりだした。髪の毛から、ぼたぼたとしずくが落ち、彼は相変らずむっつりとしていた。
突然、彼は、廻りの土器を指さして言った。
「見ろ、この土器を――これは、おら達の祖先が作ったものだ。東北人は鈍重だ。東北は文化的後進圏だと、そんなことを言う奴もいるが、これを見てみねえか――」
感慨深げに言うと、彼は部屋の片隅に行って、ガラス張りの戸棚にこまごまと置かれた小さな土器の中から一つを取った。
掌に乗せて戻って来ると、彼は、それをぼくに突き出した。
変った形の土器だった。亀の甲羅のような半球形の上部に口があり、その口の周囲に、明らかにじょうごの役割をするための囲みがあるのだ。そして、土器の下部には、土瓶のように注口がついている。かなり複雑な縄文の模様が浮きあがり、彩色の名残りと思われる澁い赤みが、重たく艶を出していた。
「いつ頃のもんだ。」と、ぼくは聞いていた。
「二千年以上も前のもんだ。じょうごの発想、土瓶の発想は、この時、すでに成されていたんだじゃ。しかも、この独創的な形、この複雑な文様は、この東北の地から発展していったんだじゃ。」
「東北?」
「そうだ。この土器は、この小湊の遺跡から発掘したもんだが、亀ヶ岡式土器の一つなんだ――亀ヶ岡式土器っていうのは、西津軽郡の木造にある亀ヶ岡遺跡からの発掘品によって名づけられたものなんだが、それは縄文晩期を代表する傑作なんだ。遠く関東の平野、山梨、長野の山岳地帯、紀伊半島、北海道の南部にも影響を与えたんだじゃ。」
彼は、ずぶ濡れの服をそのままに興奮した口調で言うと、ぼくの手から、その土器を取ってじっと見つめた。
やがて、ふっと、何かを思い出したような表情になって、彼は、さっきの戸棚に近づいた。そして、土器を戻すと、別な何かを取り出して来た。
「やあ、なつかしいじゃ。」と、ぼくはひったくるように手を取った。それは、加工場の出窓に置かれてあったあの埴輪であったからだ。
「その目を見てみろ。」と、彼は謎をかけるように言った。
「目?」と、ぼくは埴輪のそれを覗き込んだ。そして、「ああ、晶子の目はこれだったんだな。」と、思わず大声をたてた。
「そうなんだ。君と、きのう別れた後で、あっ、これだったと思いだしたんだじゃ。」
そう言うと、彼は、ようやくぼくの存在に気づいたかのように、「君、わざわざよく来てくれたなあ……今晩は、宿っていってもいいんだべ?」と話しかけるのだった。
残念なことに、終列車の時間は迫っていた。ぼくは、引きとめる彼へ、「また来るから、また来るから……」と言いながら部屋を出た。
雨は、まだ激しかった。彼は傘で、ぼくを駅まで見送ってくれた。
別れぎわ、ポツリと彼は言った。
「君に、手紙書きたくなった。住所教えてくれないか……」
速達便の長い手紙が山田陽太郎から届いたのは、翌日の昼過ぎだった。
たったさっき君と別れたばかりで、この手紙を書いている。せっかく尋ねて来たのに、自分を失してすまなかった。
今日、ぼくは、近くの台地の暮れていく遺跡に立って、雨風に身をまかせていた。そして、遠い縄文の時代に思いを走らせたのだ。
文明の世の中には、はるかに遠い竪穴住居の中で、絶え間なく襲いかかる自然現象と斗うことは実にきびしく、ひどいものだったろう。しかし、彼等は生きたのだ。その証としての遺跡は、人間の生命力の逞ましさをしみじみと感じさせるのだ。
夜学で君と知り合った頃、ぼくは生命というものにどうしようもない不信を感じていた。
実は、ぼくは親父をあの三年前に亡くし、お袋は、ぼくを連れて再婚していったのだ。
お袋が父以外の男と寐るなんて、ぼくには堪えられぬほど嫌らしいことだった。誰とだっていいんだ。そうやって人間は生まれてくるんだ――そう思ったら、ぼくは、自分自身の命に我慢できなくなった。そして、愚連隊の仲間に入っていったのだ。
秋の一日、ぼくは仲間と一緒に学校をサボり、東京の郊外にブラブラと遊びに行った。その時、ぼくらは古墳を見つけたのだ。
面白半分に、ぼくらは古墳荒らしをやった。そして、ぼくは、あの埴輪を掘り出したのだ。
生命を呼ぶかのように太鼓を叩くあどけない埴輪の目に、ぼくは打たれた。死者のほとりで、魂の不滅を信じて疑わない埴輪の一つ――虚無でくり抜かれたぼくの目にも、そのように、無心に生命を信じていく何ものかが宿ることは出来ないのだろうか……そんな思いで悶々としながら、相変らず、ずるずると不しだらな生活を続けている内に、ぼくはとうとう、母の実家へ預けられてしまったのだ。
東京で生まれ、東京で育ったぼくにとって、のっぺりとした北国の風景は我慢がならないものだった。そのうさばらしが、バフンとの対決となって現われたのかもしれない。しかし、学園の民主化という、大上段に振りかぶったあの頃のぼくの言葉には、純粋に、人と人、生命と生命が結びついていくようにという願いがあったことを、わかってくれ給え。
だが、ぼくの願いに反して、学園はつららのようだった。自から(*ママ)の願いで、内から融けていこうとする気力がそこにはないことを、ぼくは、あの講堂でバフンとやり合った時の、口をつぐんだ人々の表情に見出した。
ぼくは絶望した。しかし、ぼくはあの埴輪の目を見つめていると、その絶望から、どうしても抜け出したくなるのだった。
〝晩鐘〟という紙名が、共産党みたいだとか言われたことを、君は覚えているだろうか。そして、ぼく自身が共産主義者であり、しかも、町会議長の寄生虫だと中傷されたことを――
そのことを知らされた時、ぼくは、意味もなく乱読した本の中の、一つの言葉をふと思い出した。それは、〝万国の労働者団結せよ〟という、共産党宣言の一句であった。
ぼくは、叔父の恩恵に、なるほどあやされて、ぶらぶらと生きている自分を考えた。君をはじめ夜学の諸君は、立派に、労働者としての生活を送っているではないか。互いの生命に対する信頼と結びつきは、ぼくが、労働者として自立していく時にこそ可能となるのではないか――
ぼくはそう思った。そして、叔父の絆を絶ち切り、自分自身の力で生きるために、ぼくはあそこを飛び出した。
あれから、いろいろなことがあった。そして、ぼくはどうやら、運転手という職業に落ちついたようだ。
仕事の僅かな合間を見て、ぼくは遺跡をたずねて歩くようになった。あの埴輪が忘れられなかったわけだが、埴輪というものは近畿地方の円筒埴輪に端を発し、人物埴輪は関東地方に於いて発達したものなので、この青森ではお目にかかることが出来なかった。勿論、そういうことは、後になって知ったことなのだが……
やがて、ぼくは考古学ばかりではなく、民俗学の分野にも足を踏み入れていった。君に見せたあの注口土器の創意――限られた条件の中で生きるための必携品を産み出す、名もなき人々の智恵のすばらしさは、漁村や農村で、もはや使い忘れられたコネリバチの中にも、そして、アツシのガサガサとする感触の中にも、ぼくは見出すことが出来るからだ。
いつの間にか、ぼくの東京弁は、青森の言葉でなまっていった。東京が恋しく、侘びしくなったこともあるぼくだったが、次第に、この北の風土に密着していったのだろう。
東京といったところで、詮じ(*煎じ)つめれば、みんな何代前、何十代前には、田舎から流れていったのではないか。現に、このぼくだって、母は青森の人間だし、江戸っ子だった親父でも、家系を辿ってみたら、どこの田舎者かわかったものじゃない。
言葉のなまりと共に、ぼくは、母を許せるようになっていった。一つの風土に様々な時の転移があったように、母の一生にも、様々な出来事があるべきなのだろう……
こうして、母は許せたが、しかし、ぼくはもう、東京に戻りたいとは思っていない。亀ヶ岡文化を築き上げた、この北国の魂の系譜に、ぼくは、連なっていくことを選んだのだ。
しかし、考古学や民俗学をやっていくために、ぼくの障害はあまりに多い。高校さえ卒業しなかったぼくは、大学の研究室を主流とする学問の現状に於いて、末流も末流、ひどい末流だ。あんなふうに図書館を借りて展示をしてみたが、学問の世界から見る時、あれはただあれだけのことに過ぎない。あの資料から、どのような仮説を導き出すかということ――その仮説にかかった信憑性の度合いが問題なのだ。でも、それは、ぼく一人の力には過ぎることだ。
図書館で、すぐれた研究者と話し合っている内に、ひどく自分のやっていることが虚しくなって、ぼくは家へ戻ると、ふらふらと行きなれた遺跡へ向かって行った。そして、風雨にさらされ、暮れていく台地の上で、ぼくは自分に言い聞かせたのだ。例え、机上の理論を築き上げることが出来なくてもいいではないか。ぼくは今、自分の肌で、名もなき人々の歴史、生命の讃歌を感じとっている――これでいい、これでいいのだと、自分自身に言い聞かせた……
運転手という商売は、ひどい労働条件の下におかれている。今、ぼくは、仲間を集めて労働組合を作るための準備をひそかに進めているが、いずれにしても、こんな中でやれる研究はたかが知れているだろう。そして、ぼくはこれからも、あの台地で感じとった姿勢だけは崩さずに、出来る限りのことはまとめ上げていきたい。
最後になったが、今度の参院選挙には、日本共産党に一票を投じてくれ給え。
三十日夜 雨は、もう止んでいる。
山 田 陽 太 郎
石 塚 健 一 君
「日本共産党……」と、ぼくは思わず呟やいた。
不意に書かれたその一言は、彼の告白のしめくくりには、ふさわしいもののようであった。
ぼくは、山田陽太郎との、短かった夜学での交友をしみじみと思い浮かべていた。
〝晩鐘〟が共産党のようだとけなされた時、ぼくらは火炎瓶のイメージに色濃く左右されて憤ったものだった。しかし、加工場の一室に寄り合い、学園の民主化に頬を火照らせた、ぼくらの青臭く、一途な心は、火炎瓶と五十歩百歩のものだったのではないか――そして、ぼくが、あの青春の一齣を受け入れるなら、日本共産党を受け入れてならない理由はない……
あんな辺鄙な土地にいながら、ぼくの青春は、時代の青春と一つだったのだ。そして、ぼくが今、新しい季節へと抜け出ていこうとする時、党もまた、ぼくと一つになって羽ばたくのではないだろうか……
貧乏だった、そして、今もなお変らぬぼく自身の生活を噛みしめながら、ぼくは、「日本共産党……」と、再び呟やいた。
「ニポ、ニポ。」と、晶子の声がした。
ぼくの言葉を真似ながら、晶子は、ぼくの手から、山田陽太郎の手紙を引張りとろうとする。
ぼくは、晶子の顔を覗き込んだ。
レモンのような、埴輪の目が笑っている……
東北人のこのぼくの血を受け、アイヌの血を好江から受け、そして、はるか関東の一隅で出土したあの埴輪の目を持って生まれた晶子――
時代や人種を超えた生命の流れが、彼女の目から、ぼくの心にゆるやかに伝わってくるのを感じながら、ぼくは晶子を抱きしめていた。そして、晶子の上に、日本共産党は、まるで一つの人格のように、像を結ぼうとゆらぐのだった。
そのゆらめきの中で、山田陽太郎と、木下の顔が、もつれ合って浮かんでいた。
あとがき
● たった一篇の小説を載せて、雑誌でございますと名乗るのは、例によって気がひける。自家製版、自家印刷、自家製本という、こんな手工業的な苦労をしなくても、文学賞を狙って、ナマ原稿を投函すれば済むものを……
● しかし、ぼくにすれば、海のものとも、山のものともつかぬ作品が一人、二人の、予選選者の目を通り抜けてオクラになってしまうのは、忍びないことなのだ。一つ一つの作品には、それなりに、ぼくの苦しい愛着がある。個人雑誌という形を借りたささやかな伝達機関によって、読んで貰いたい人に読んで貰えるこの方法は、ぼくにとって止むに止まれぬものである。
● 今号は、四十部印刷した。少くとも、四十人の人には読んで貰えるわけだ。この費用は、郵送料を含めて約二千円である。高い身銭を切って我が家の経済をおびやかすようではあるが、これでも、同人誌に参加するよりは安上がりだ。二等級七号俸の薄給をいただく一家の主人としては、当分、この形式で我慢するより他はない。
● 第一号に発表した「御料牧場」は、幸いにも、「文学界」の同人雑誌評で、ベスト5に選ばれることが出来た。しかし、久保田正文氏がそこで「せっかちな結論を出さず、問題の出し放しでいい。」というような意味を言われ、ぼくの弱点をつかれる時、ぼくは淋しくなってしまうのだ。なぜなら、ぼくを文学に駆りたたせるものは、無意味な人生に意味を見出し、現実を恋人のように抱きしめたいという衝動なのだから……文学は、ぼくにとって、そのような「手」として存在するのだ。
● 雑誌「部落」の東上高志氏より同作品を転載したい旨の手紙をいただいた。光栄である。ぼくはこれからも、自分自身の痛みを通して、「部落(コタン)」の姿を考えていきたい。
「手」三号より全文を掲載。1966年2月発行。
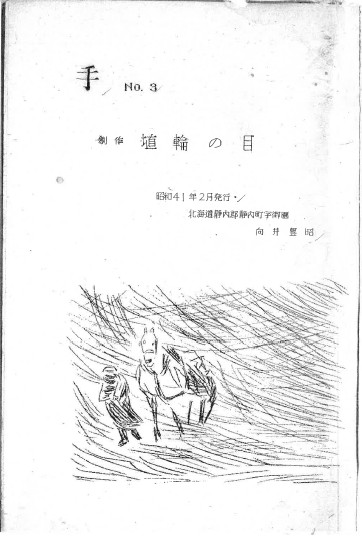
入力ノート
誤りとされるような用字は「*ママ」として残した。
※「狭」「挟」などの字の旁はすべて「夾」の挾狹
※「紐」の旁は「刃」に下線がある字体
※「寝」はすべて「寐」表記
※簿は略字で書かれているのを推測で埋めた
*1 原稿では「光」に似た略字 文脈から「興」と判断。以下同じ。